
2024年の土用の丑(うし) の日はいつ?意味や由来、うなぎ以外に食べるものも紹介
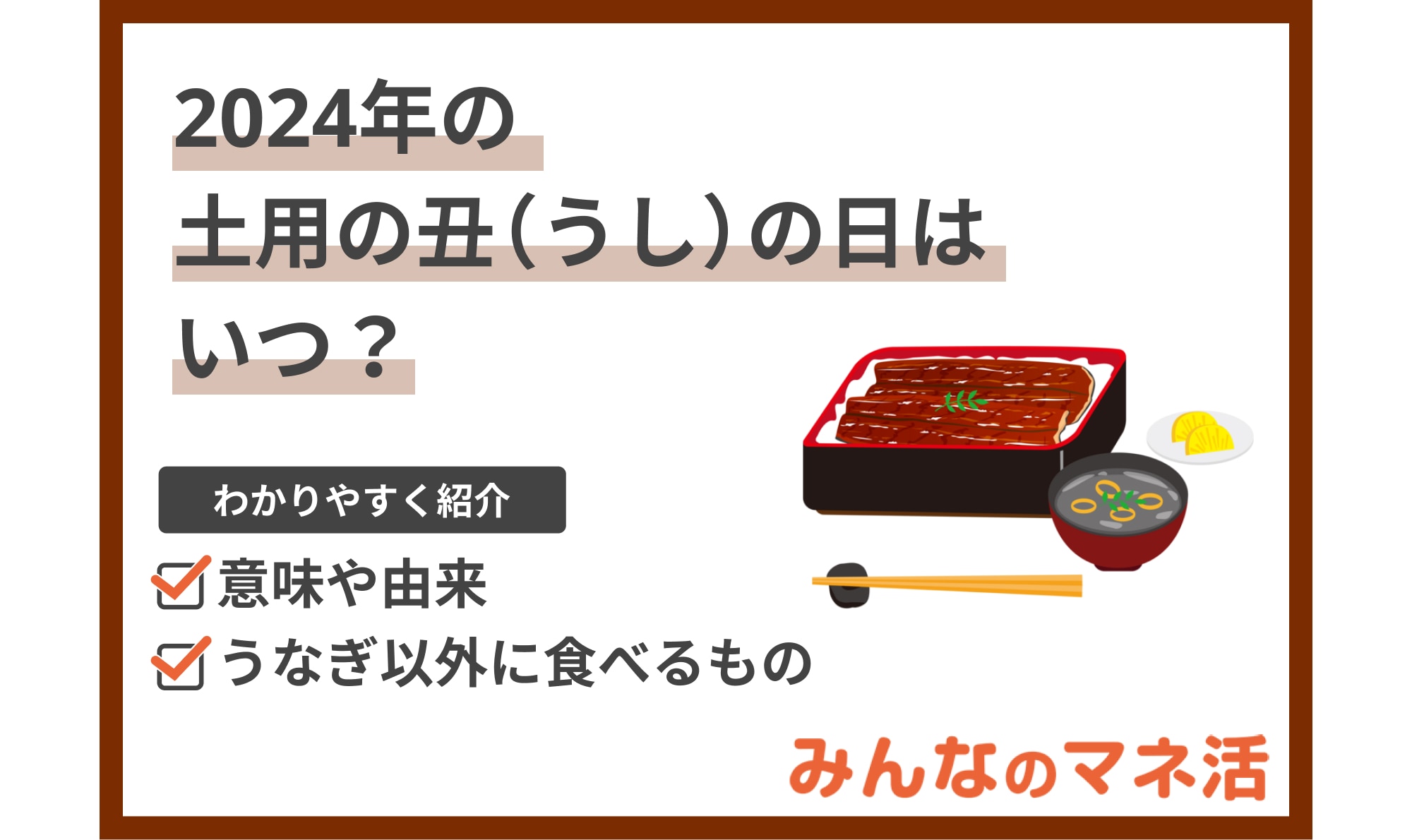
梅雨が明け、夏が本格的に始まる頃に土用の丑の日がやってきます。「今年もうなぎの季節がやってきた」「うなぎを食べて夏の暑さを乗り切ろう」と考える方も多いでしょう。
しかし、土用の丑の日になぜうなぎを食べるのか、その由来をご存知でしょうか。また、土用の丑の日には、うなぎ以外にも食べると良いとされているものがあります。
2024年の夏の土用の丑の日は7月24日(水)と8月5日(月)です。由来や意味を知ったうえで、おいしいうなぎを堪能し夏の暑さを乗り切りましょう。


-
年会費が永年無料
-
100円につき1ポイント貯まる※1
-
新規入会&3回利用で
もれなく5,000ポイント※2
- ※1 一部ポイント還元の対象外、または還元率が異なる場合がございます。ポイント還元について詳細を見る
- ※2 新規入会特典2,000ポイント(通常ポイント)、カード利用特典3,000ポイント(期間限定ポイント)特典の進呈条件について詳細を見る
- ※2 「3回以上利用」は常時開催中の企画によるものであり、利用回数の条件は期間によって変更される場合があります。
- ※2 3,000ポイントは常時開催中の企画によるものであり、ポイント数は期間によって変更される場合があります。
- 土用の丑の日はいつ?
- 土用の丑の日にうなぎを食べるようになった由来
- 地域別のうなぎの食べ方
- 土用の丑の日に食べるうなぎ以外の食べ物
- 土用に行われる風習・禁忌事項
- 土用の丑の日にはうなぎを食べて夏を乗り切りましょう
土用の丑の日はいつ?
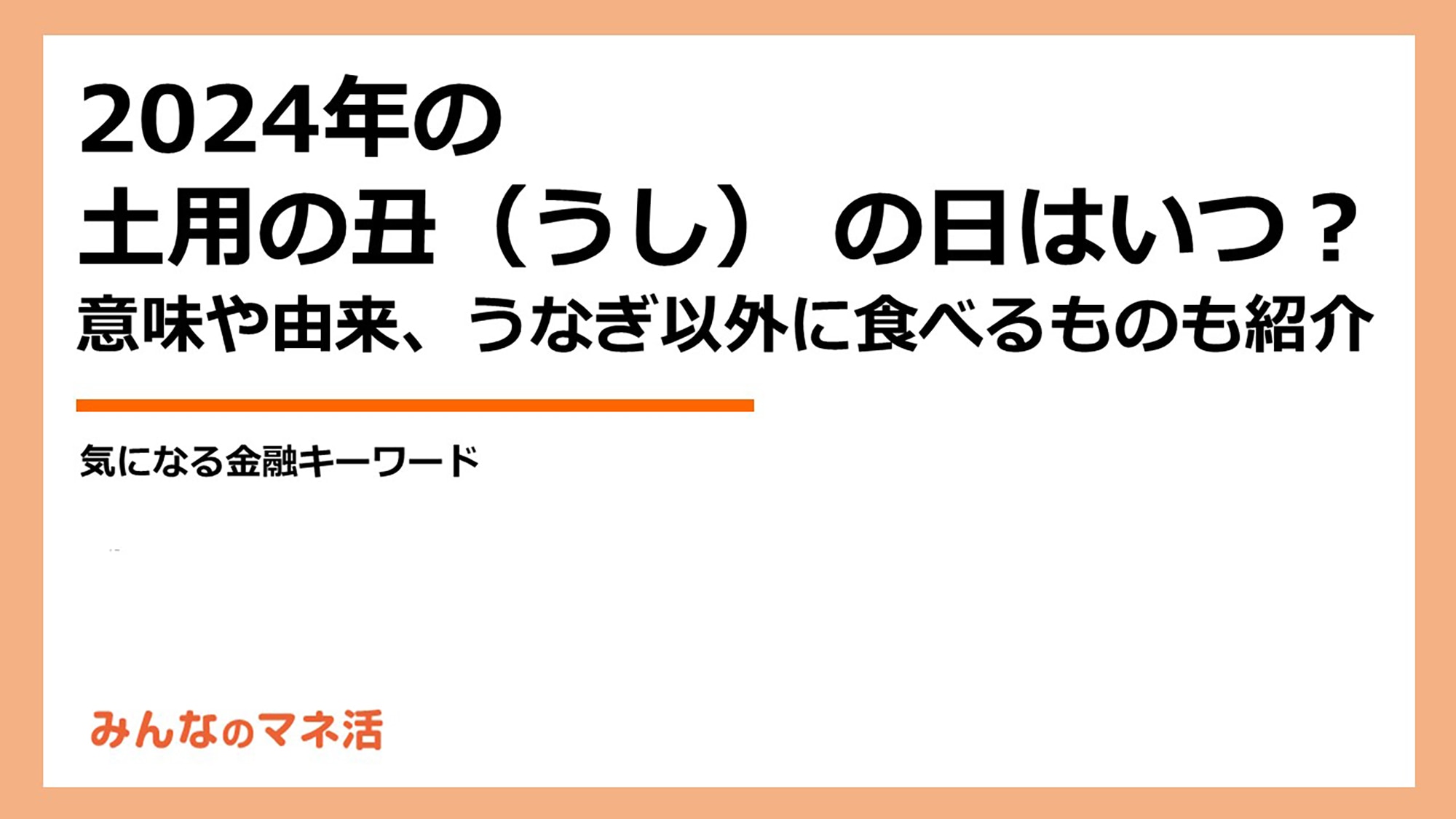
土用の丑の日は夏にしかないと思われがちですが、実は四季を通して年に6回あります。
2024年の土用の丑の日と土用期間は以下のとおりです。
| 季節 | 土用の丑の日 | 土用期間 |
| 冬 | 1月26日(金) | 1月18日~2月3日 |
| 春 | 4月19日(金) 5月1日(水) |
4月16日~5月4日 |
| 夏 | 7月24日(水) 8月5日(月) |
7月19日~8月6日 |
| 秋 | 10月28日(月) | 10月20日~11月6日 |
なお、土用期間の中で土用の丑の日が2回ある場合、1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」といい、2024年は春と夏に二の丑があります。
土用の丑の日とは?
そもそも「土用」と「丑の日」にはどのような意味があるのでしょうか。それぞれの由来や名前の意味を解説します。
土用
「土用」は、中国に古くから伝わる「陰陽五行思想(陰陽五行説)」に由来するとされています。陰陽五行思想では、万物の根源は木・火・土・金・水の5つの元素にあると考えられています。
季節もこれに対応させて、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」としました。しかし、「土」がどこにも当てはまらないため、季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前18日間に割り当てられることになったのです。この期間を土用といいます。
土用は、日本独自の季節の目安となる「雑節」のひとつで、古来より人々に季節の移り変わりを伝えてきたといわれています。
丑の日
「丑の日」は、日にちを十二支で数えたときに、丑に当たる日です。丑の日は12日周期で回ってきます。年を表わす際の「十二支」はよく知られていますが、「丑」は日にちや時刻や方角を表す際にも利用されています。
土用の丑の日とは「土用期間内」に訪れる「丑の日」です。
土用の丑の日にうなぎを食べるようになった由来

現在、土用の丑の日にはうなぎを食べる風習が根付いていますが、なぜうなぎが食べられるようになったのでしょうか。
その由来には、「平賀源内説」と「夏の暑さに耐えるための対策説」の2つの説があります(諸説あり)。
平賀源内説
江戸時代に、本草学(中国の薬物学)者・地質学者・蘭学者・医者など幅広い分野で業績を残した、平賀源内のアイデアによるものという説が挙げられます。
当時のうなぎの旬は秋から冬とされており、夏場の脂がのったうなぎは好まれませんでした。
売れ行きの悪さに困ったうなぎ屋の店主は、発明家としても有名な平賀源内に「夏にうなぎを食べてもらうにはどうしたら良いか?」と相談しました。平賀源内の助言により店先に「本日、土用の丑の日はうなぎの日」という張り紙をしたところ、集客に成功したのです。
うなぎ屋の繁盛を見てほかのうなぎ屋も真似するようになり、徐々に夏の土用の丑の日にはうなぎを食べることが定着したとされています。
夏の暑さに耐えるための対策説
平賀源内がうなぎを広めるより以前から、日本では夏にうなぎを食べる習慣がありました。
うなぎを食べると元気が出るというイメージのとおり、うなぎにはビタミンA群・B群がたっぷり含まれているため、疲れた体のリカバリーや、食欲の増進が期待できます。
日本人にとって夏にうなぎを食べることは、夏バテ防止に効果的だったと考えられます。
うなぎを食べて、夏の暑さを乗り切ろうという、古くからの食習慣がありました。
なお万葉集には、大伴家持が詠んだ「石麻呂に われ物申す 夏痩せに良しといふ物そ 鰻取り食(め)せ」という歌が収められています。すでに奈良時代には、うなぎが夏バテに効果があると認識されていたようです。
|
|
|
地域別のうなぎの食べ方

うなぎの食べ方は、関東と関西で異なります。主な違いはうなぎの「さばき方」と「焼き方」です。
さばき方の違い
うなぎをさばく際、関東では背中に包丁を入れる「背開き」に、関西ではおなかに包丁を入れる「腹開き」にすることが多いです。
関東では武士の考え方である「切腹」を連想させおなかを切ることは縁起が悪いとされ、背開きが多かったとされています。
一方、関西では商人に根付く、「商売には腹を割って話し合うことが大事だ」といった考えなどから、腹開きが多かったようです。
また、頭を落とすタイミングも異なり、関西では最初に落とすことが多く、関西では焼き上がり後に落とすことが多いです。
焼き方の違い
関東では、うなぎを白焼きにして蒸してから焼き上げます。白焼きにした後に蒸すと、余分な脂が落ちふっくらと柔らかく仕上がるのです。
関西では、白焼きを蒸さずにそのまま焼きます。蒸さずに焼くだけで、香ばしい皮の風味と身の柔らかい食感を楽しめます。
土用の丑の日に食べるうなぎ以外の食べ物

土用の丑の日といえばうなぎが有名ですが、旬の食材や頭に「う」のつく食材など、うなぎ以外にも食べられているものがあります。
土用しじみ
しじみは冬と夏に旬を迎え、冬のしじみを寒しじみ、夏のしじみを土用しじみといいます。
しじみには、肝機能を高めるオルニチンが豊富に含まれており、土用シジミは産卵前の時期に当たるため栄養価が高いといわれています。「土用しじみは腹薬」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
また、うなぎは高価な食材ですが、しじみはうなぎよりもリーズナブルなため、手軽に食事に取り入れられます。
土用卵
土用期間中に産まれた卵を「土用卵」といいます。卵には良質なタンパク質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれているため、完全栄養食とされ、特に土用卵は高い栄養価があるといわれています。
つまり、うなぎと同様に夏バテ防止に効果的な食材なのです。
また、さまざまな料理にアレンジできるのも特徴で、うなぎを芯にして巻いた「う巻き」も夏におすすめのメニューです。
「う」のつく食べ物
頭に「う」の付く食べ物も、土用の丑の日に食べると良いとされています。例えば、以下の食材が挙げられます。
- うどん
- 梅干し
- ウリ(瓜)
- 牛肉や馬肉
- 黒ゴマや黒豆など黒いもの
うどんはのど越しが良く、食欲が出ない夏にも食べやすい食材です。また、梅干しに含まれるクエン酸は疲労回復効果があるほか、唾液が出ることで食欲増進にもつながります。
ウリ科の野菜(ウリ・キュウリ・スイカ・かぼちゃなど)は水分やカリウムが豊富なため、身体にこもった熱を冷ます効果があります。
また、「うし」である牛肉や「うま」である馬肉も精のつく食材として夏におすすめです。
土用に行われる風習・禁忌事項

土用にはうなぎなどを食べるほかにも、生活におけるさまざまな風習があります。また、土用の時期に避けるべきとされていることも併せて確認しましょう。
土用の丑の日の風習
土用の丑の日には、「土用の虫干し」や「丑湯」といった風習があります。
土用の虫干しは、梅雨により湿気を帯びた衣類や布団、書物、家具などを、風に当てて干すことを指します。
夏の土用は梅雨明けのタイミングと重なるため、ものを干すのに良い時期です。干すことで、湿気だけでなくカビや害虫を予防できます。
また、夏バテ防止のために、薬草入りのお風呂に入ることを丑湯といいます。ヨモギや桃の葉、ハッカなどが薬草として利用されていた時代もあったようです。
熱い薬草のお風呂につかることで、疲労回復だけでなく無病息災を願う気持ちにもつながっています。
土用には避けた方が良いこと
土用には、「土いじり」や「新しく何かを始める」「場所の移動」など、避けたほうが良いことがあります。
土用期間中は、土を司る神様である「土公神(どくじん・どこうしん)」が支配する期間と考えられています。土公神が地上にいらっしゃる間は土が最も働く期間とされ、土は動かさないように配慮が必要です。
また、土用期間中は季節の変わり目であり、体調を崩しやすい期間です。そのため、新規事業の開始や結婚、転職・就職など、新しいことを始めない方が良いといわれています。
ほかにも、新居の購入や引越しなどの移動も控えたほうが良いとされています。特に、「土用殺(どようさつ)」方位への移動は凶とされています。土用殺方位は季節ごとに変わり、夏土用は「南西」への移動を避けたほうが良いでしょう。
土用の丑の日にはうなぎを食べて夏を乗り切りましょう

古来、人々は土用の丑の日にうなぎなどの栄養価の高い食材を食べて、夏バテに打ち勝つ体力をつけてきました。風習は現代にも引き継がれ、夏の土用の丑の日にはうなぎを食べることが習慣となっています。
また、うなぎだけでなく土用しじみや土用卵、「う」の付く食べ物など、土用の丑の日に進んで摂取したい食材があります。
虫干しや丑湯などの風習も取り入れながら、夏の暑い時期を上手に乗り切りましょう。
なお、土用の丑の日に外食でうなぎを食べに行くと、お店が混んでいることが予想されるでしょう。今年はおうちでうなぎを楽しむのもひとつの選択肢です。楽天市場には、さまざまなうなぎ商品があります。楽天ふるさと納税を活用すれば、納税しながらおいしいうなぎをいただくことも可能です。



-
年会費が永年無料
-
100円につき1ポイント貯まる※1
-
新規入会&3回利用で
もれなく5,000ポイント※2
- ※1 一部ポイント還元の対象外、または還元率が異なる場合がございます。ポイント還元について詳細を見る
- ※2 新規入会特典2,000ポイント(通常ポイント)、カード利用特典3,000ポイント(期間限定ポイント)特典の進呈条件について詳細を見る
- ※2 「3回以上利用」は常時開催中の企画によるものであり、利用回数の条件は期間によって変更される場合があります。
- ※2 3,000ポイントは常時開催中の企画によるものであり、ポイント数は期間によって変更される場合があります。
このテーマに関する気になるポイント!
-
2024年の土用の丑の日はいつ?
年に6回ありますが、夏の土用の丑の日は7月24日(水)と8月5日(月)です。
-
土用の丑の日にうなぎを食べるようになった由来は?
平賀源内のアイデア説や夏バテ防止説などいくつかの由来があります。
-
うなぎ以外に食べられているものはある?
土用しじみや土用卵のほか、うどんなどの「う」の付くものなどが食べられています。
-
食べ物以外の風習は?
「土用の虫干し」や「丑湯」といった風習があります。

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
この記事をチェックした人にはコチラ!
|
|
|








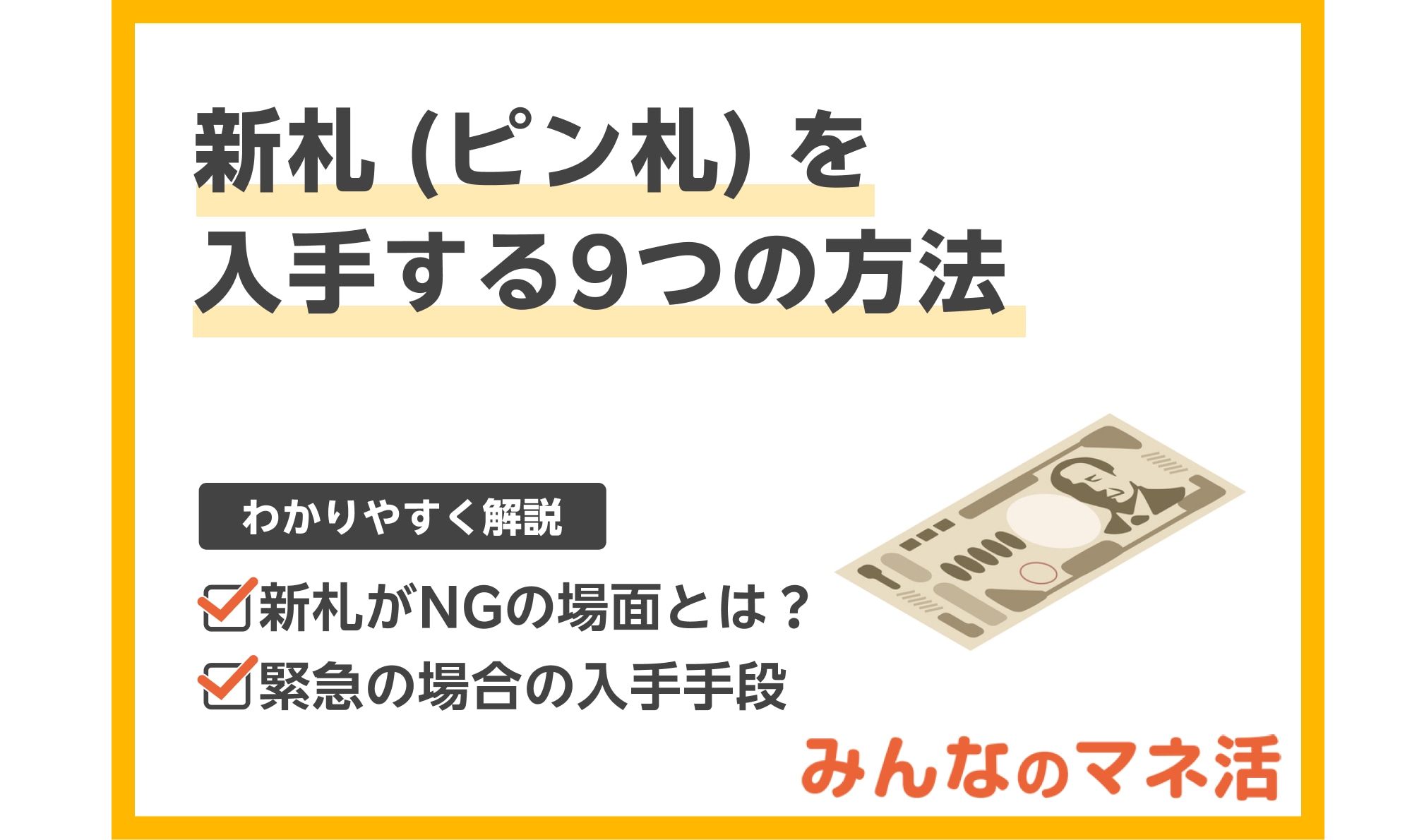


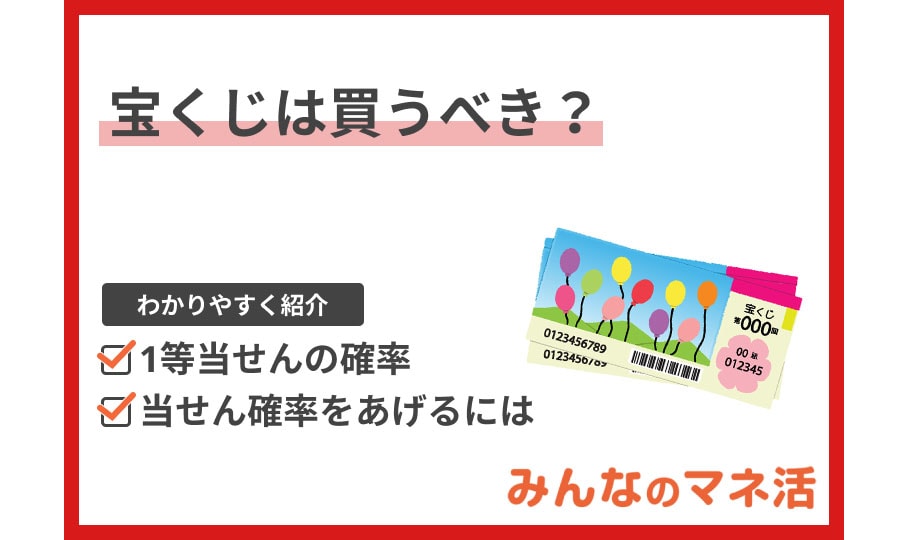



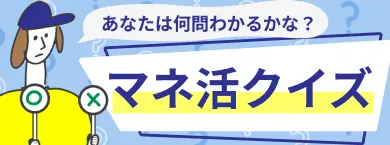
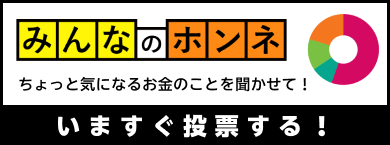
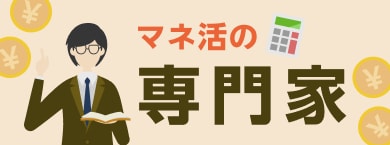








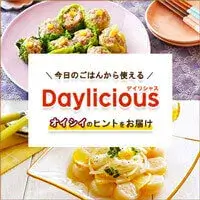




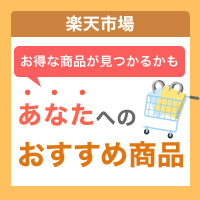
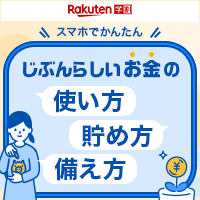
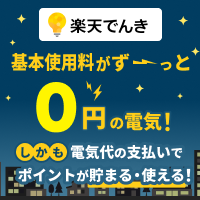


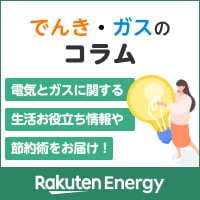
土用は夏だけじゃなくて季節ごとにあるのね!