楽天カードの種類まとめ!各カードの特徴とお得なポイントとは?
アンガーマネジメントとは|診断タイプを解説。効果や怒りの感情を抑える方法も

アンガーマネジメントは、「怒り」の感情と上手く付き合うためのトレーニングです。怒りが発生するメカニズムとそれをコントロールする実践的なテクニックを知って、仕事や人間関係での失敗を減らすのに役立てましょう。


-
年会費が永年無料
-
100円につき1ポイント貯まる※1
-
新規入会&利用で
もれなく5,000ポイント※2
- ※1 一部ポイント還元の対象外、または還元率が異なる場合がございます。ポイント還元について詳細を見る
- ※2 新規入会特典2,000ポイント(通常ポイント)、カード利用特典3,000ポイント(期間限定ポイント)特典の進呈条件について詳細を見る
- アンガーマネジメントとは
- そもそも怒りの感情のメカニズムとは
- アンガーマネジメントはなぜ必要?(怒ることのデメリット)
- アンガーマネジメントの効果(アンガーマネジメントのメリット)
- アンガーマネジメント診断でわかるあなたの怒りタイプ
- アンガーマネジメント実践法
アンガーマネジメントとは
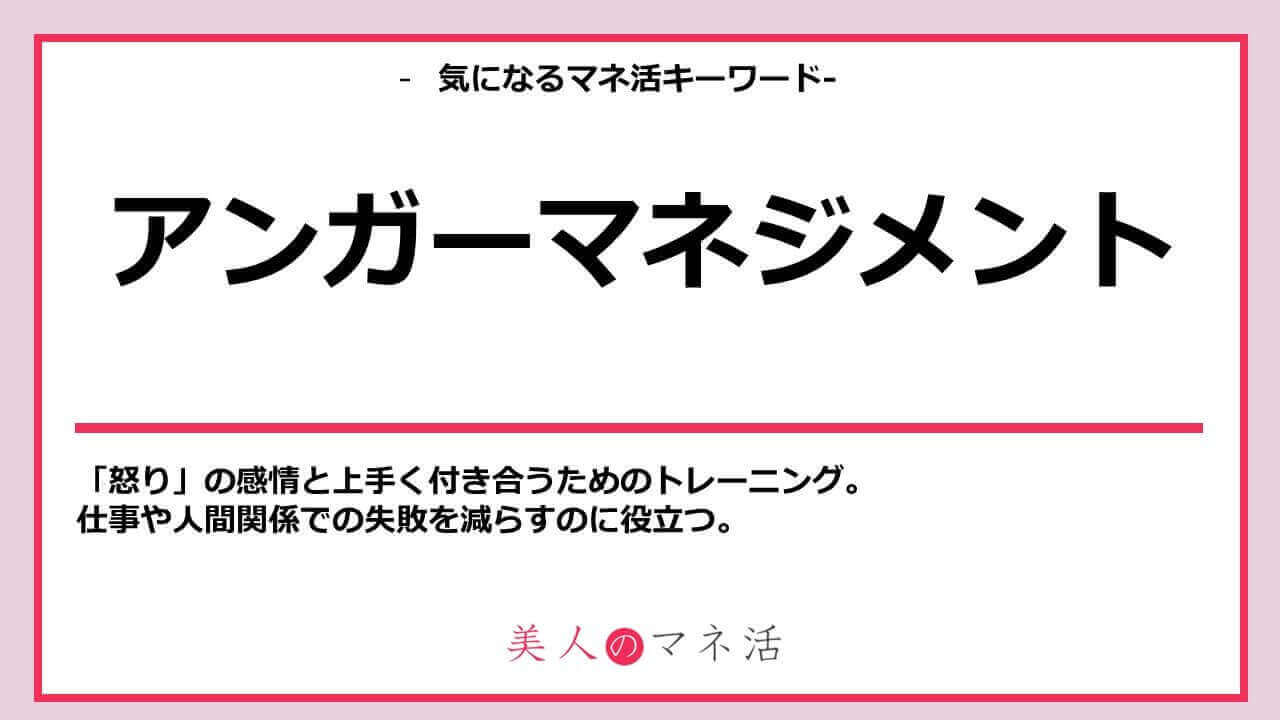
アンガーマネジメントは「怒り」の感情を、どのようにコントロールするか学ぶトレーニングです。英語で書くと「Anger Management」。そのまま訳すと「怒りの管理」や「怒りの制御」といった意味になります。もともとは1970年代の米国で始まった心理教育。犯罪者を対象とした、矯正プログラムの一環として実施されていました。たしかに暴力を伴う犯罪には「怒り」の感情を制御できないことに、その原因の一部分があると考えられるでしょう。
現在においては、アンガーマネジメントは広く一般的なトレーニングとして行われています。さまざまな価値観が共存する現代社会。それぞれの価値観がぶつかり合い、怒りが生まれてしまう場面も増えているようです。怒りの感情とどう付き合えば良いのか、悩んでいる人も多いのかもしれません。また、ビジネスの場面でもアンガーマネジメントは重要です。人間関係の改善やパワハラの予防など、社員教育の一環として実施されることもあります。
そもそも怒りの感情のメカニズムとは

・第1次感情と第2次感情
怒りの感情はどのようなプロセスによって発生するのでしょうか。アンガーマネジメントの考えでは、そのメカニズムを説明する際に「第1次感情」「第2次感情」という概念を使っています。
私たちは普段の生活の中で、さまざまなネガティブな感情を、心の中に溜め込んでしまうことがあります。「なんだか疲れてしまった」「将来に不安を感じる」「心配ごとが絶えない」「この仕事はつらい」といった感情です。こうした心に溜まっているネガティブな感情を「第1次感情」と呼んでいます。
そして第1次感情が溜まりすぎてしまったとき、発生しやすくなるのが「怒り」の感情。この怒りの感情は「第2次感情」と呼ばれています。
つまりアンガーマネジメントにおいては単に怒りそのものを見るのではなく、その背後にある第1次感情の蓄積に着目しているということです。自分が怒りっぽい状態だと感じるときは、心の中の第1次感情を意識してみると良いかもしれません。不安や疲労など、怒りをコントロールするために改善すべきポイントが見つかる可能性があります。
・怒りのきっかけとなるのは「価値観のギャップ」
人にはそれぞれ「こうあるべき」という価値観や理想があります。たとえば「人は礼儀正しくあるべき」という価値観を持った人がいるとしましょう。態度が悪い人と接することで、その価値観を裏切られることが怒りのきっかけとなるのです。また仕事上で頼んでおいたことについて、理想から大きく離れた結果が出てきたとしましょう。もしネガティブな第1次感情が溜まっている状態であれば、イライラしてすぐに怒りが爆発しそうになると思います。
怒りのメカニズムをイメージする際、アンガーマネジメントではライターにたとえることがあります。ライターに火をつけるには、燃料となるガスが必要です。この燃料となるのが、日ごろ溜め込んだネガティブな第1次感情。これが多いほど、怒りの火がよく燃えるというわけです。
そして着火のタイミングとなるのが、価値観のギャップによるストレス。自分と周囲との間にある考え方の違いも、怒りの管理においては、意識すべき重要なポイントとなるようです。
アンガーマネジメントはなぜ必要?(怒ることのデメリット)

コントロールされていない怒りは、周囲との人間関係を悪くしてしまいます。感情に任せて大きな声を出してしまったり、良くない言葉を相手にぶつけてしまったりするからです。たとえば家庭において、子どもが思わしくない行動を取ったとき、冷静になれず怒りをぶつけたとしましょう。こうしたことが続けば、親子関係が悪化する原因になりかねません。
職場でも同じです。周囲のミスに怒りを感じることがあるかもしれませんが、その怒りをストレートに出してしまうとチームは機能しなくなるでしょう。最近では、職場でのパワーハラスメントも問題視されています。
怒りをコントロールできない状態は、自分自身にも悪い影響を及ぼします。怒ってイライラしている時間が長引けば、自分の中にもストレスが溜まります。その影響で体調が悪くなってしまうかもしれません。また周囲に人がいない場合でも、怒りをコントロールできなければ物に当たってしまうこともあります。怒りに任せて物を投げつけた結果、大切にしている物を壊してしまうことがあります。
自動車の運転などでも、怒りには気をつけたいところ。他の自動車の動きに腹を立てて、危険な運転をしてしまうことがあります。怒りが事故や犯罪につながることもあるのです。制御できない怒りは対人関係でも自分自身にとってもデメリットばかりと言えるでしょう。
アンガーマネジメントの効果(アンガーマネジメントのメリット)
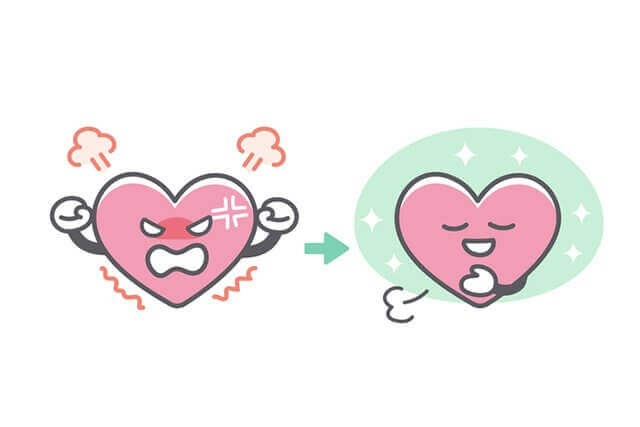
怒りのメカニズムを考えたとき、怒りのきっかけとなっていたのが「価値観のギャップ」でした。自分が正しいと思うことがあり、それと異なることが起こったときに怒りに火が付くというものです。
アンガーマネジメントができていない状況では、この価値観のギャップを意識できていないのかもしれません。怒りが管理できていれば、自分がどんな価値観を持っているのか、なぜ怒っているのかわかるようになるでしょう。自分と異なる価値観への理解も進むと思われます。
また不安や苦痛など、自分の中に蓄積されている第1次感情を意識することで、心の健康管理にも役立ちそうです。怒りっぽい自分に気付いたら、まずその原因をチェックすると良いでしょう。
アンガーマネジメントにより、自分の中にある怒りをコントロールできるようになれば、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。怒りの原因を理性的に把握し、それを合理的に解決する方向に行動できます。怒りをぶつけていると、周囲の人との関係を悪化させてしまいますが、アンガーマネジメントにより、こうした悪影響を避けることができるでしょう。怒りをコントロールすれば、チームワークを保ったまま問題の解決へ向かうことができるのです。
アンガーマネジメント診断でわかるあなたの怒りタイプ
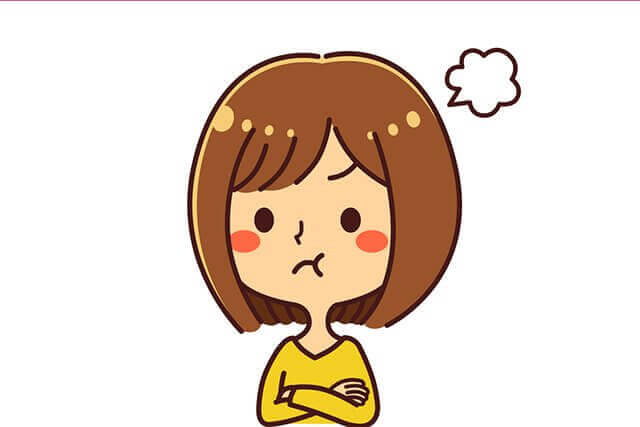
日本アンガーマネジメント協会によれば、怒りは6つのタイプに分類されます。「天真爛漫(てんしんらんまん)」「威風堂々(いふうどうどう)」「用心堅固(ようじんけんご)」「外柔内剛(がいじゅうないごう)」「公明正大(こうめいせいだい)」・「博学多才(はくがくたさい)」の6つです。すべて4文字熟語で表されていますが、それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。
・天真爛漫
天真爛漫タイプが持っているのは、自由な行動やストレートな発言を重視するという価値観。自分の行動や発言に制限を受けることや、はっきりと意見を言えない相手などに怒りを感じます。
・威風堂々
自分の正しさに自信を持っていて、プライドが高い性格と分析されます。自分の意見が否定されたときや、周囲からネガティブな評価を受けていると感じたときに、怒りの感情が強くなります。
・用心堅固
まじめで慎重、周囲への警戒感が強いタイプです。他人からの干渉に対して、怒りやストレスを強く感じます。
・外柔内剛
人当たりは穏やかなのですが、自分自身で決めたルールは曲げない性格とみられます。自分のルールに反したことをしなければならないことや、周囲が自分のルールから外れたことをしているのを見ることが怒りのきっかけとなります。
・公明正大
道徳やマナーにこだわりのあるタイプ。正義感が強く、周囲のマナー違反などにイライラを感じます。
・博学多才
このタイプは向上心が強い完璧主義者。周囲の優柔不断な言動や、中途半端な行動などに対して強い怒りの感情を持ちます。
アンガーマネジメント実践法

・6秒ルール
怒りをコントロールする方法としてよく言われているのが「6秒ルール」。強い怒りを感じ始めたら、6秒は我慢して、声を出したり行動に移したりしないようにします。怒りの感情は6秒間たつとピークを超えるようで、そこを乗り越えれば大きな失敗につながるようなことをせずに済むということです。
怒りの原因となるようなことが起こった瞬間、反射的に爆発してしまうのは避けたいもの。まずは6秒間じっと我慢する習慣をつけると良いのかもしれません。
・ネガティブな感情の解消
アンガーマネジメントのために、普段から実践できることもあります。怒りのメカニズムには、その原因となるエネルギーとしてネガティブな第1次感情の蓄積がありました。音楽を聴いたり運動をしたり、リラックスすることでマイナスの感情を減らしておくことができるでしょう。
・自分の怒りのパターンを客観的に眺める
また怒りのきっかけとなるのが、価値観のギャップ。自分の中の「こうあるべき」という考えにはどんなものがあるのか、リストアップして把握しておくことが対策となります。
怒りを感じる場面があれば、そこから離れてみるというのも1つの手段です。1人で冷静になる時間を作りやすくなるでしょう。気持ちを落ち着かせるということであれば、深呼吸が有効です。6秒ルールで怒りを我慢している間に行えば、よりリラックスした状態へ近づけるかもしれません。
自分の怒りを客観的にとらえる方法としては「怒りの点数化」があります。今の自分の怒りが、10段階でどれくらいなのかを点数化して、低い点数なら、怒りの感情を表に出す必要がないと判断できるでしょう。
株やFXなどの金融取引でも、損をすると後悔とともに怒りがこみ上げるということがあるかもしれません。怒りに身を任せて自暴自棄になれば、さらに損失を重ねる可能性もあります。お金に関してもアンガーマネジメントは重要です。楽天ブックスで「アンガーマネジメント」を検索すると、たくさんの関連書籍をみつけることができます。怒りがコントロールできるようになれば、さまざまな場面で失敗を減らせそうです。
また、お金に関する不安や悩み。こうしたことも「怒り」を引き起こす燃料としての第1次感情になる可能性があります。お金について学び、不安を少なくしていくことも、アンガーマネジメントに役立つでしょう。
このテーマに関する気になるポイント!
-
アンガーマネジメントとは何?
「怒り」の感情と上手く付き合うためのトレーニングです。
-
そもそも怒りの感情のメカニズムとはどんなもの?
ネガティブ感情が溜まったところに、価値観のギャップがきっかけとなり「怒り」の感情が生まれます。
-
アンガーマネジメントはなぜ必要?
仕事や人間関係での失敗を避けるために必要です。
-
アンガーマネジメントの効果は?
自分と他人との間にある価値観の違いを認識し、自分の怒りをコントロールできるようになることです。
-
怒りのタイプにはどんなものがある?
怒りを感じやすい要因によって、天真爛漫・威風堂々・用心堅固・外柔内剛・公明正大・博学多才の6タイプに分類されます。
-
アンガーマネジメントの実践方法は?
怒りを6秒間我慢することで感情的になるのを抑える「6秒ルール」などがあります。
この記事をチェックした人におすすめの記事 |
|
|
|

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。












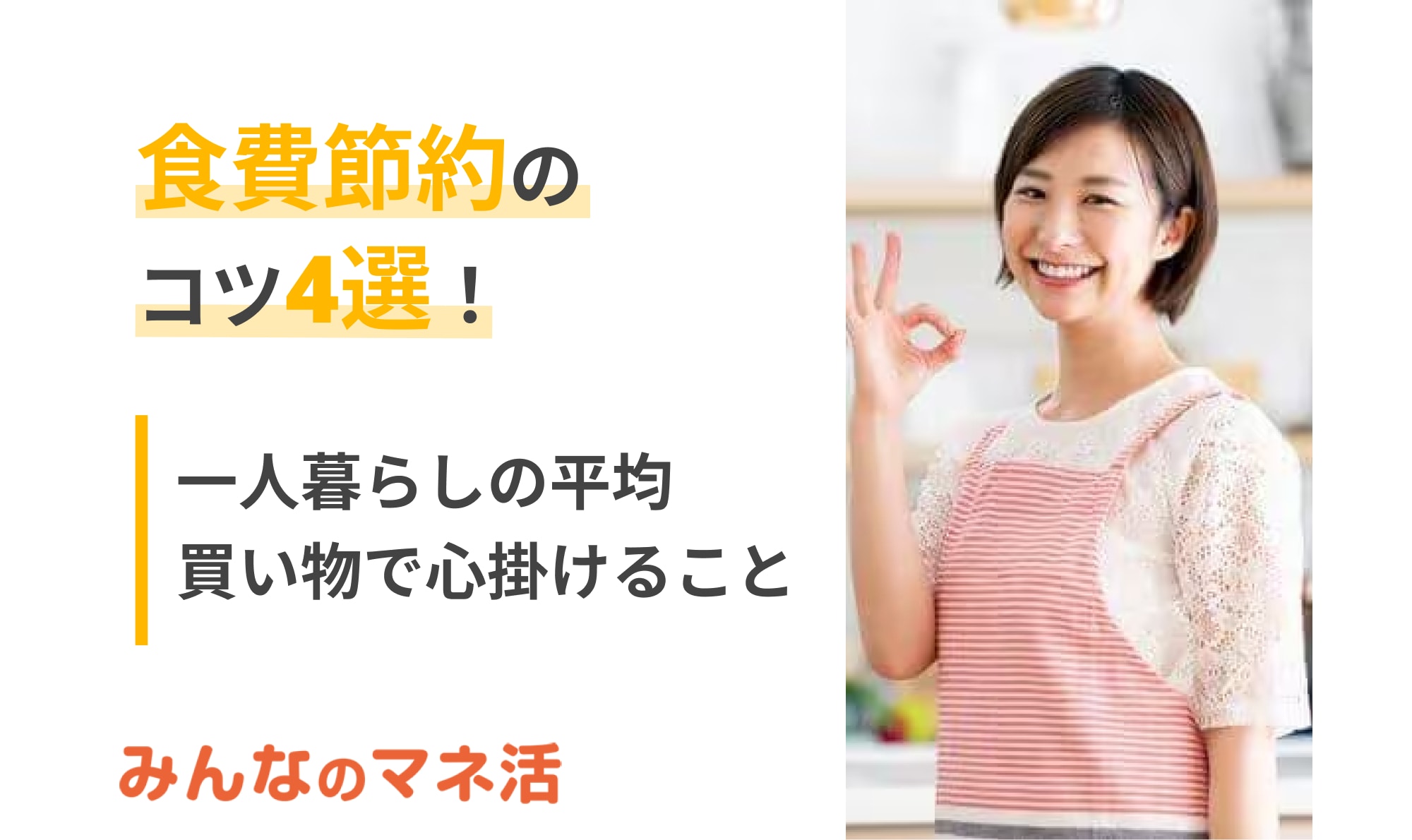




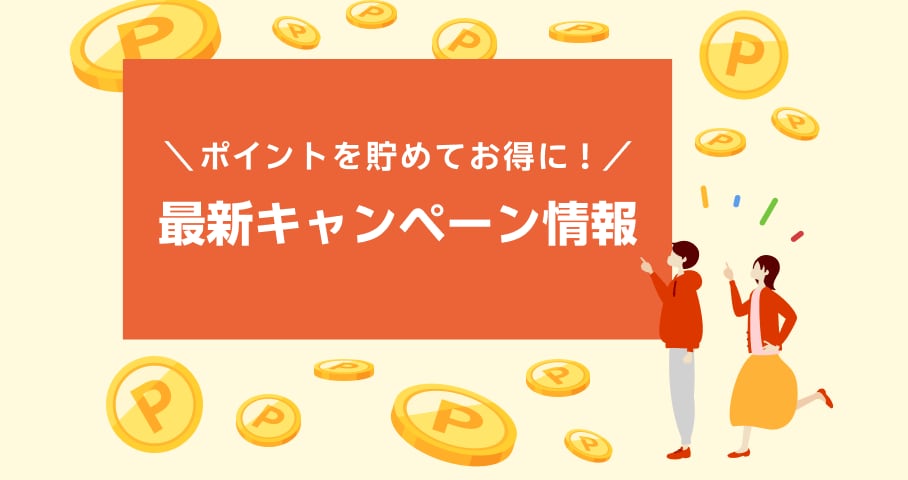


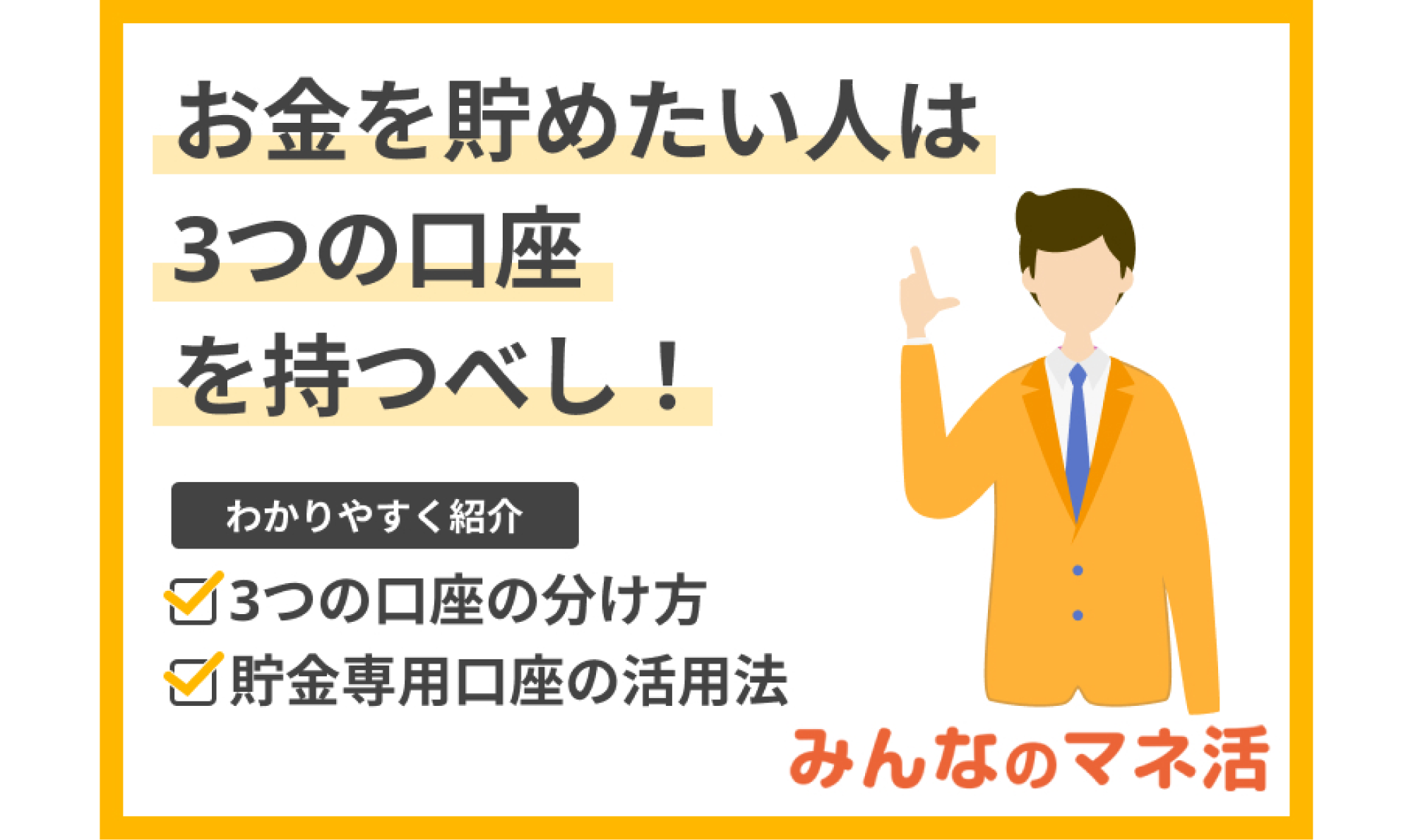
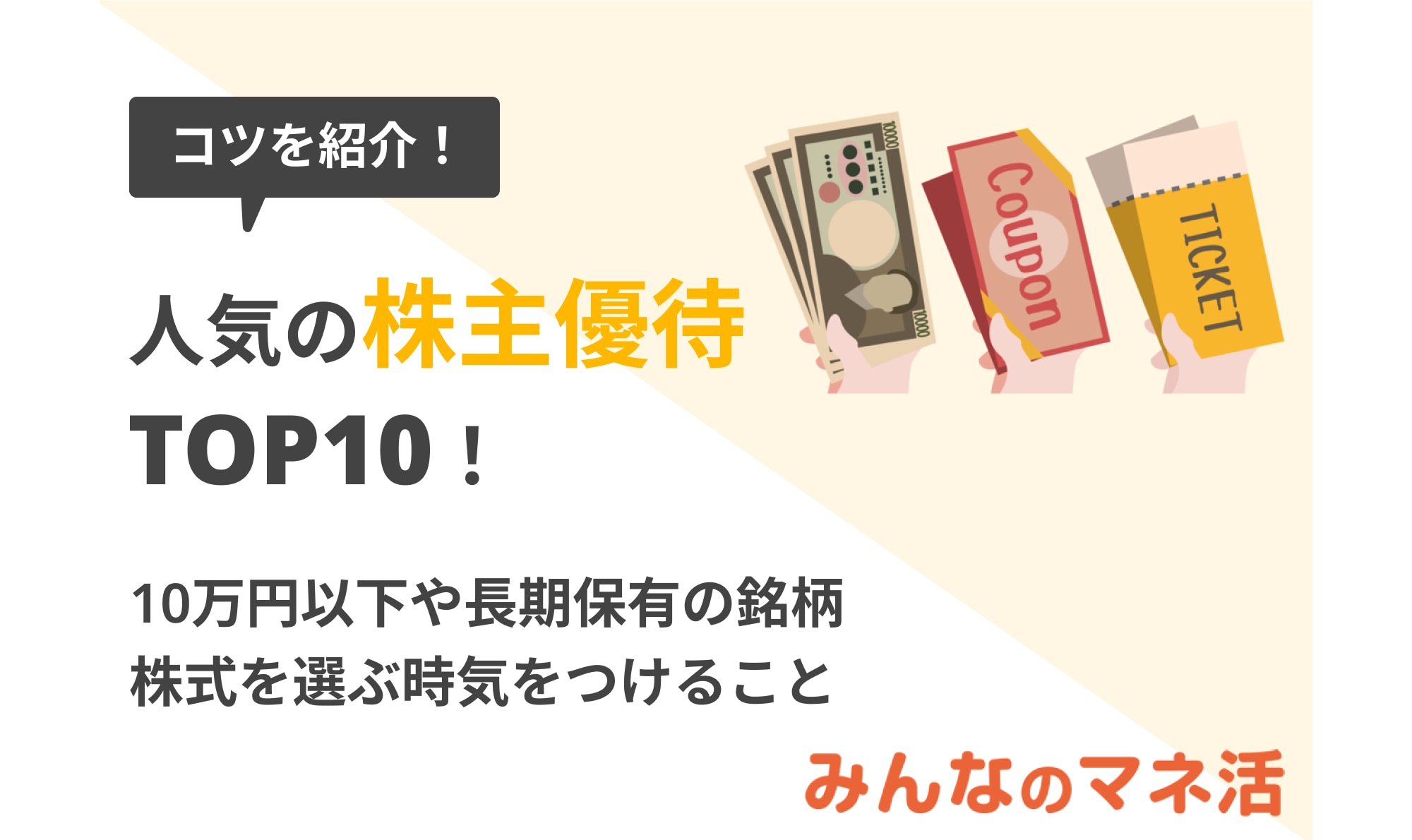



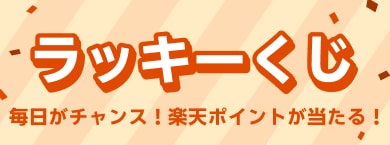


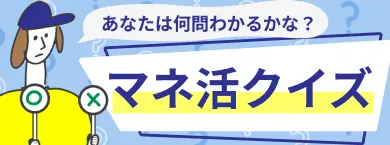
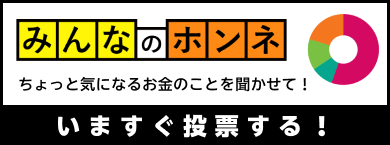
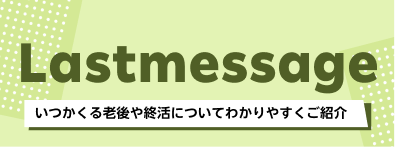
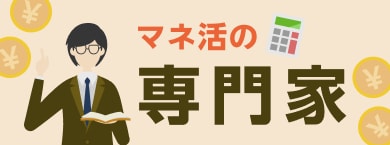








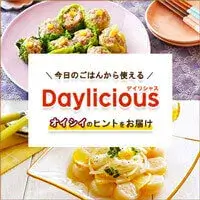




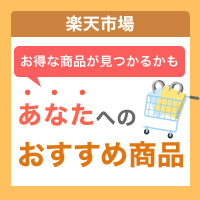
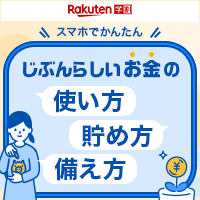
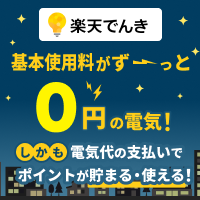


これって大事かも!頭に血が上りそうなときは、まず落ち着いて冷静になれるといいわよね