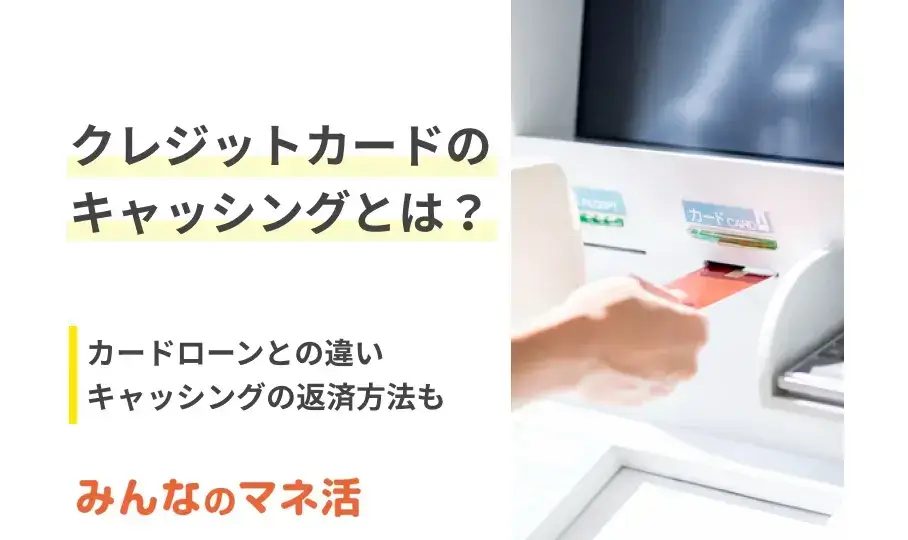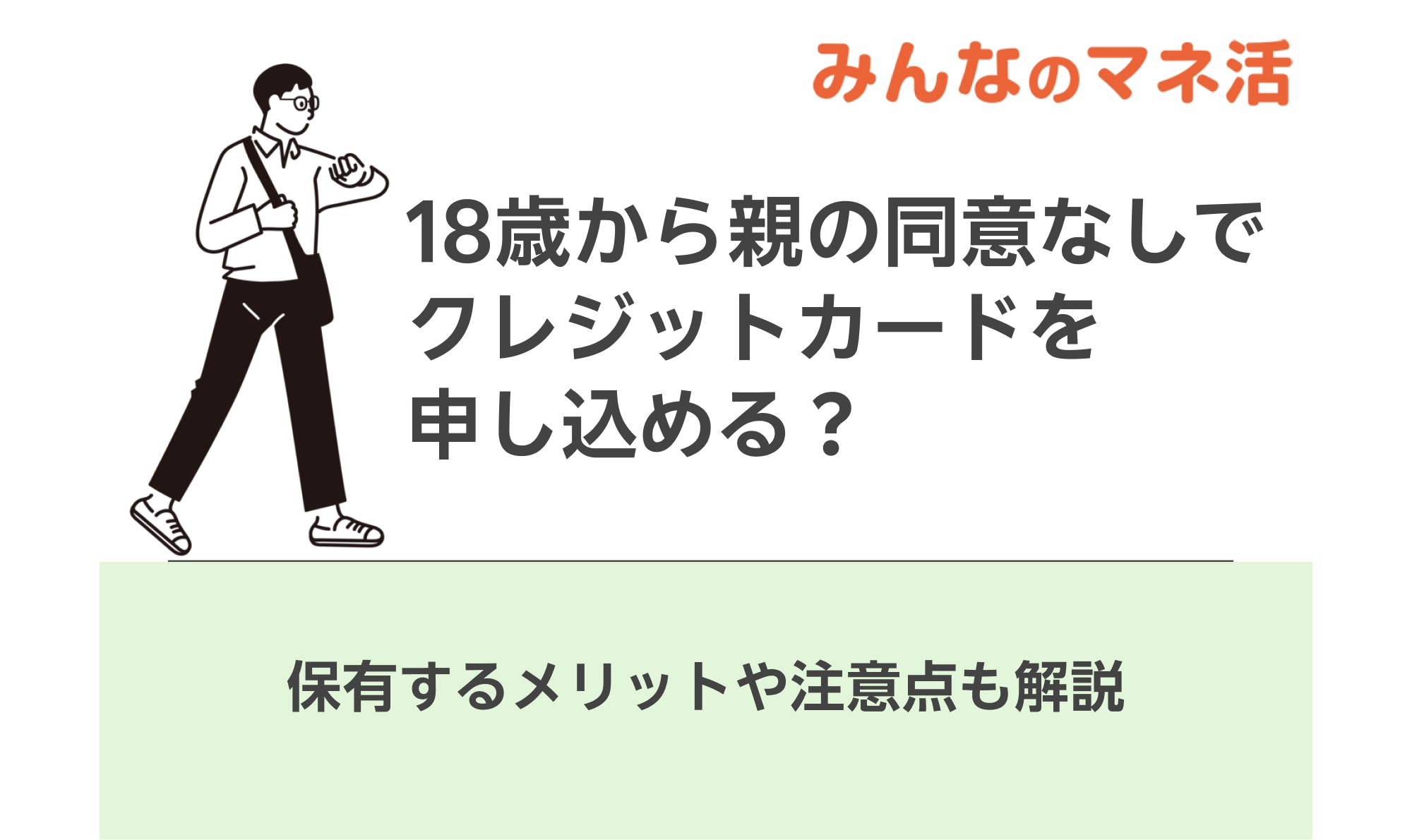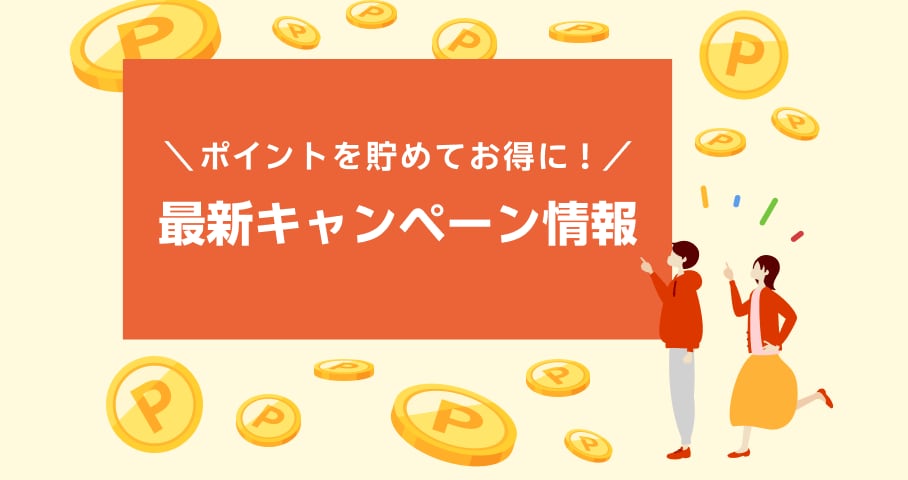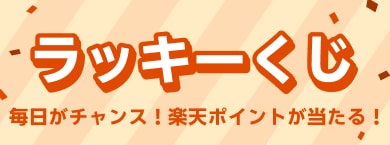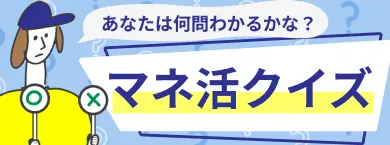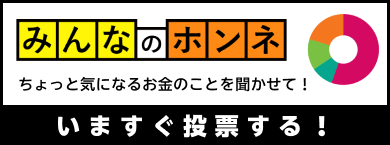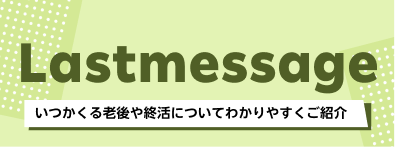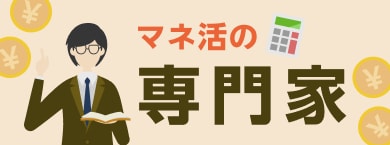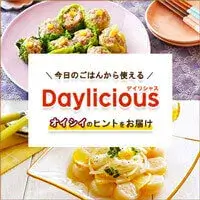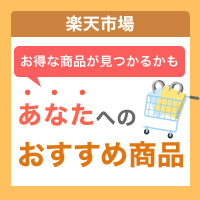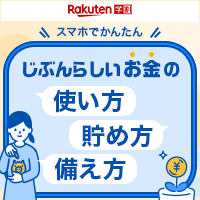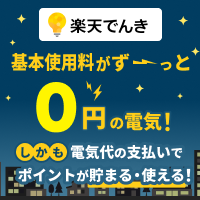楽天証券でiDeCoを始めるには何が必要?iDeCoの特徴や注意点などを解説
個人年金でいくら受け取れる?商品の種類、仕組みや控除額を解説

公的年金のみでは不安な老後に対し、個人年金でも備えたいと思っている人もいるでしょう。ここでは、個人年金でいくら受け取れるのか、商品の種類や仕組み、控除額についても解説していきます。将来設計の参考にしてみてください。
- 個人年金とは
- 個人年金の種類
- 公的年金以外の備えが必要な理由
- 個人年金の受取額のシミュレーション
- 個人年金のメリット・デメリット
- 人によって違う?選ぶべき個人年金
- 個人年金で節税もできてしまう?
- 個人年金には確定申告が必要?
個人年金とは

個人年金とは、公的年金に上乗せして年金を受け取りたい個人が加入する年金です。公的年金は基礎年金と厚生年金の二階建てになっており、その上に企業型確定拠出年金(DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)といった私的年金があります。個人年金という場合、通常、これらの公的年金、私的年金とは別に保険会社が提供する商品の「個人年金保険」のことをいいます。
個人年金保険では保険会社が加入者から預かったお金を運用し、年金として支払います。個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合、運営管理機関に加入手続き後、加入した運営管理機関を通して任意の金融商品自分でを選ぶことになります。
個人年金の種類

個人年金には運用方法、受け取り方、受け取る金額が定額か変額などの種類があります。それぞれの特徴を説明していきます。
運用方法
外貨建て
変額個人年金では、運用益に応じて将来受け取れる金額が変わります。運用方法を外貨建てにすることでよりアクティブな利回りを期待したり、円安やインフレといった価値変動に備えたりすることができます。ただし、外貨建てを利用すると円から外貨、外貨から円にする両替手数料がかかります。また、為替変動リスクも考慮せねばならないため注意が必要です。
円建て
個人年金の運用方法で円建てを選択すると受け取れる年金額をあらかじめ把握しやすくなるなどのメリットがあります。一方、外貨建て運用に比べて運用成果が低くなりやすいなどの注意点もあります。
受け取り方
確定年金
確定年金は、契約時に定めた一定期間は確実に年金を受け取れるというものです。例えば、確定10年の個人年金に加入していた場合、受取期間中に被保険者が亡くなってしまったとしても、以降の年金を遺族などが受け取れます。
有期年金
有期年金は確定年金と同じく定めた一定期間年金を受け取るものですが、年金受取開始後に被保険者が死んでしまうと、遺族が残されていたとしてもそれ以降の年金は受け取れなくなってしまいます。ただし、保証期間付の商品を契約した場合は、保証期間中に被保険者が死んでしまっても遺族が年金を受け取れるケースもあります。
終身年金
終身年金は一生涯年金を受け取ることが可能ですが、掛金は高くなる傾向があるため注意が必要です。
受け取る金額
定額型
個人年金には定額型と変額型があります。「定額個人年金保険」は契約時に定めた予定利率により積立運用を行うものです。将来受け取る年金額が確定、もしくは最低保証されており、途中解約や保険会社が破綻したりしない限り元本割れの可能性は少ないでしょう。
変額型
一方「変額個人年金保険」は保険会社が株式や債券などで資産運用を行います。運用実績が良ければ年金の受取金額が増える見込みもありますが、元本割れをするリスクもあることを理解しておきましょう。
|
|
|
公的年金以外の備えが必要な理由

2024年度の国民年金の月額は満額の場合で6万8,000円です。しかし、1カ月の収入が6万8,000円のみと考えると、かなり苦しい生活を想定しなければなりません。
現役時代に厚生年金にも加入していた場合、2024年度の受給額の平均は国民年金と厚生年金の合計で標準的な夫婦ふたりで約23万483円です。ここから国民健康保険料や介護保険料、各種税金などを支払うことになり、実際の生活に使える金額はさらに少なくなると考えるべきです。
これらを見ていくと老後の生活費が年金だけでは賄えない場合が多く、貯蓄や個人年金などを使ってあらかじめお金を準備しておく必要があることがわかります。
個人で老後の資金を準備するには個人年金以外にも、銀行預金やiDeCo、NISAを活用した資産運用などさまざまな手段が考えられます。老後の備えで、全員に当てはまる正解というものはありません。さまざまな情報を吟味しながら、収入や生活スタイルにあわせて考えることが必要です。
個人年金の受取額のシミュレーション

個人年金に加入した場合の将来の受取額は、各保険会社のホームページに資料が掲載されていたり、シミュレーションしたりすることができます。細かな条件なども参考にしながらチェックしてみましょう。
個人年金のメリット・デメリット
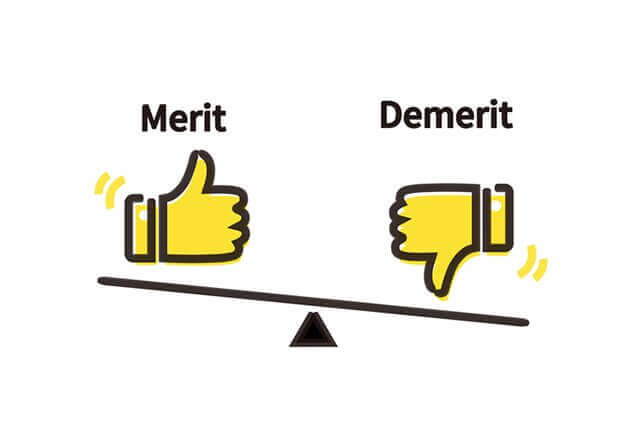
個人年金のメリットとデメリットを説明いたします。
個人年金のメリット

- 生命保険料控除が受けられる
- 月々保険料を払い込むことで将来に備えられる
- 銀行預金と異なり容易に引き出しできないことで強制力がある
- 銀行預金よりも利回りが良いとされる
生命保険料控除が受けられる
個人年金の中には、年末調整や確定申告での生命保険料控除を受けられるものもあります。ただし、生命保険料控除を受けるには条件を満たす必要があるため事前に確認するようにしましょう。
月々保険料を払い込むことで将来に備えられる
個人年金では月々保険会社に保険料を払い込むことが将来受け取れる年金額の積み立てとなっています。計画的な貯金が苦手という人にもおすすめです。
銀行預金と異なり容易に引き出しが容易にできないことでから貯蓄の強制力がある
個人年金で払い込んでいたお金を動かしたい場合、解約手続きを行う必要があります。銀行預金などと違いすぐには引き出しが行えないことも、強制力に繋がり安心でしょう。ただし、途中で解約した場合払い込んだ金額が元本割れしてしまう可能性があります。
銀行預金よりも利回りが良いとされる
個人年金では銀行預金以上の利率が期待でき、また保険の種類や受け取り方によって返礼率が異なります。ただし、中には元本保証されないものもあるため注意が必要です。
個人年金のデメリット

- 将来的に起きるインフレやデフレには対応しづらい
- 急に現金が必要になった場合に引き出しづらい
- 途中で解約すると元本割れする可能性がある
将来的に起きるインフレやデフレには対応しづらい
あらかじめ受け取る年金額が決まっているタイプの個人年金の場合、インフレやデフレといった物価の変動には対応しづらいというデメリットがあります。
急に現金が必要になった場合に引き出しづらい
個人年金で払い込んだお金を動かしたい場合、保険の解約手続きが必要になります。解約がしづらいことはメリットでもある一方、デメリットにもなり得るでしょう。
途中で解約すると元本割れする可能性がある
個人年金を途中で解約した場合、払い込んだ金額から元本割れをする可能性があります。契約時によく確認しましょう。
個人年金は年金として積み立てた金額を受け取るまでに長い期間があり、その間月々の保険料を支払わないといけません。収入の中から保険料分の金額を差し引いても毎日の生活が成り立つという人でなければ、個人年金を無理なく活用することは難しいでしょう。
ただ、個人年金を契約中に急にお金が必要になった場合、個人年金を解約するのではなく、保険会社の行っている契約者向けの貸付などを利用することでカバーができることもあります。ただ、一般的にはカードローンより金利は低めに設定されているものの、貸付を利用すると利息がかかってしまうことに注意が必要です。
個人年金は、お金が貯まるとつい使ってしまう、なかなか計画的にお金を貯められないという人におすすめです。これらの人にとっては、途中で解約すると元本割れしてしまうというデメリットが、逆に貯蓄の強制力としてのメリットになるかもしれません。
人によって違う?選ぶべき個人年金

個人年金に加入する際は、家族構成が大きなポイントになってきます。
独身で、自分ひとりの老後のためだけに個人年金に加入するのであれば、自身がどのようなリスクに備えたいか、退職後の空白期間をカバーしたいのか、長生きリスクに備えたいのかなどを考えて選びましょう。
一方、配偶者がいる場合は、確定年金を選ぶことに大きなメリットがあります。例えば、夫が65歳(現役時代は会社員)、妻が60歳(専業主婦)の夫婦の場合です。夫が65歳で退職をした際に妻はまだ年金が受け取れないため、妻が年金を受け取れる65歳になるまでの5年間は夫の年金と貯金で生活をすることになります。
この期間に夫が亡くなってしまった場合、妻の収入は夫の遺族年金だけになってしまいます。令和6年4月分からの遺族基礎年金は年に81万6,000円(月額6万8,000円)。夫が厚生年金の被保険者だった際に上乗せとして受け取れる遺族厚生年金は夫の月収によって異なりますが、いずれにしても夫の生きていた時よりも生活が苦しくなることが予想されます。
また、注意しておきたいのは遺族厚生年金の対象者が「子のある配偶者」、「子のない配偶者」が含まれるのに対し、遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」、「子」である点です。子のいない配偶者の場合は遺族厚生年金しか受給できず、生活が苦しくなる可能性もあります。
こうした場合にも、仮に夫が70歳まで受け取れる確定年金に加入していれば、残っている分の年金を妻が受け取ることができます。妻が65歳になり自分の年金を受給開始するまでの間、生活費の足しにすることができるでしょう。
このように、個人年金を選ぶ際はそれぞれのライフプランや資産状況、家族の状況などを総合的に考えることが大切です。長く保険料を支払う将来のための年金だからこそ、安易に契約してしまうと途中解約で大幅に損をすることになりかねないため注意しましょう。
個人年金で節税もできてしまう?

個人年金では「保険料払込期間が10年以上」などといった条件を満たすことで、生命保険料控除を受けることができます。生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払うと一定金額の所得控除を受けることができる仕組みです。
個人年金の場合、所得控除を受けられる額は年間の支払保険料によって変化します。新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合、年間に払い込んだ保険料が8万円を超えると、一律で4万円が控除されます。
また、所得税だけでなく、住民税でも控除を受けることが可能です。住民税の場合は地域によって若干異なる場合もありますが、東京都港区の場合は年間に払い込んだ保険料額が5万6,000円を超えると一律で2万8,000円が控除されます。
個人年金には確定申告が必要?

個人年金の生命保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告で申請を行う必要があります。保険料を支払っている間に所得税と住民税の節税効果が得られることは、将来の受け取りと同じくらいの個人年金のメリットといえるでしょう。
ただし、所得税も住民税も控除される金額には上限があり、払い込んだ保険料の掛金のうちの一部です。
何らかの形で貯蓄を行い、老後や万が一の場合に備えることは人生で必要不可欠といえます。
節税の観点に着目するのであれば、所得控除に上限のある個人年金よりも掛金の全額が控除されるiDeCoの方が有利といえます。iDeCoを最大限運用することで、より大きな備えと節税を行うことができるでしょう。また、自身の状況によってはiDeCoとあわせてNISAなども検討してみましょう。こちらも運用益を非課税で受け取ることのできる口座のため、資産運用ができて節税にもなります。

楽天証券の口座開設をすると、おすすめのマネー本・マネー雑誌が無料で読めます。さらに、iDeCoやNISAの口座を開設すると、冊数が増量されるので、おすすめです。また、条件を満たすことで楽天ポイントを貯めたり、金融商品の購入時に楽天ポイントを使うことも可能です(iDeCo対象外)。貯まった楽天ポイントでお買い物をするのも、再投資をしてさらに資産を増やすのも自由です。簡単に資産を管理できるスマートフォンアプリ「iGrow™」も人気。チェックしてみてはいかがでしょうか。
※この記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しております。
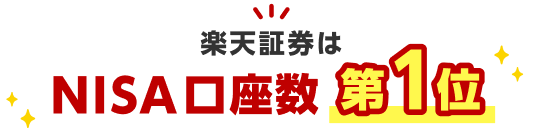

※NISA口座数 楽天証券第1位:日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料等より算出(2024年3月末時点)


PR楽天証券からのご案内です。
このテーマに関する気になるポイント!
-
個人年金とは?
公的年金に上乗せして年金を受け取りたい個人が加入する年金です。通常、保険会社が提供する「個人年金保険」の商品をいいます。
-
個人年金にはどんな積み立て方がある?
円建てと外貨建てがあります。
-
個人年金の受け取り方にはどんなものがある?
確定年金、有期年金、終身年金があります。
-
確定年金とは?
契約時に定めた一定期間、年金を受け取れるタイプの商品です。個人年金保険の受取期間中に被保険者が亡くなってしまった場合、遺族などが残りの年金を受け取れます。
-
有期年金とは?
年金の受取期間中に被保険者が亡くなってしまった場合、以降の年金が受け取れなくなるものです。ですが、保証期間付の商品を契約した場合、期間中に被保険者が死んでしまっても遺族は年金を受け取れるケースもあります。
-
終身保険とは?
一生涯年金の受け取りを続けられる保険です。掛金は高くなる傾向があります。
-
定額個人年金保険とは?
将来受け取る年金額が確定もしくは最低保証されている商品です。
-
変額個人年金保険とは?
価格変動の大きな金融商品を使って年金を運用し、高い運用益を期待する商品です。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。なお、本コンテンツは、弊社が信頼する著者が作成したものですが、情報の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問等には一切お答えいたしかねます。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
この記事をチェックした人におすすめの記事 |
|
|
|

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。