生命保険料控除とは?いくら戻るのか、計算方法や適用限度額をわかりやすく解説
生命保険料控除とは?確定申告の計算方法や上限額など解説

生命保険料控除は所得控除の一種で、支払った保険金に応じて所得税や住民税が軽減される制度です。この控除には旧契約と新契約があり、それぞれ上限額や計算方法が異なります。
ここでは、具体的にいくら税金が軽減されるのか、支払った保険料ごとに詳しく解説します。
- 所得控除の基礎知識
- 生命保険料控除とは
- 生命保険料控除の種類と対象
- 生命保険料控除の新契約と旧契約
- 生命保険料控除の計算式
- 生命保険料控除で具体的にいくら得をする?
- 年末調整や確定申告は漏れのないように申請しよう
所得控除の基礎知識

生命保険料控除は、所得控除の一種です。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に課税対象となる所得から差し引かれる金額です。
式で表すと、こうなります。
仮に所得100万円、所得税率5%の人がいたとしましょう。所得控除が0円とすると、所得税は
100万円×5%=5万円です。
もしも所得控除が10万円だとしたら、所得税は
(100万円-10万円)×5%=4万5,000円
で、5,000円の節税になりました。
ざっくりいえば、所得控除の分だけ税金がかからなくなり、全体の税額が安くなります。
生命保険料控除とは

生命保険料控除を使えば、1年間に支払った生命保険料に応じて所得税と住民税が安くなります。生命保険料全額が所得控除になるわけではありませんが、保険料を支払った人は利用したほうがお得です。
申請方法は、会社員と個人事業主で異なります。
会社員の場合
会社員の場合、概算の所得税額は毎月の給与から源泉徴収されています。そのため、年末調整で一年間の所得税額を確定し、12月の給与で清算します。会社側は年末調整の計算において社員が支払った生命保険料の金額を正確に知る必要があるため、年末調整書類には生命保険料の支払証明書を添付する必要があります。
年末調整で会社への申告ができなかった場合、確定申告を行うことで生命保険料控除が受けられます。所得税や住民税の負担を軽くするために、忘れずに申告を行うようにしましょう。
個人事業主の場合
個人事業主は、2月中旬から3月中旬の間に確定申告で所得税額を計算する必要があります。その計算の中で、支払った生命保険料を記入し、控除を受けるようにしましょう。
また、会社員、個人事業主ともに所得税の計算をもとに住民税の計算も行われるので、翌年支払う住民税にも生命保険料控除が反映されます。
|
|
|
生命保険料控除の種類と対象

生命保険料控除の対象となる保険料は、保証内容ごとに以下の3つの区分に分けられます。
一般生命保険料控除
生存または死亡に基因して、一定額の保険金やそのほかの給付金を支払うことを約する部分にかかる保険料
介護医療保険料控除
入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料
自分の加入している生命保険がどの保険料に区分され、どの控除が適用できるかは保障内容によって異なります。生命保険会社に確認をするようにしましょう。
生命保険料控除の対象外になる保険
生命保険と同様の契約でも、以下のように控除の対象にならない保険があります。
- 保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済
- 外国の生命保険会社や損害保険会社と、国外において締結したもの
- 信用保険
- 傷害保険
- 財形貯蓄
生命保険料の対象となる保険については国税庁のWebサイトに要件が記載されているため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
生命保険料控除の新契約と旧契約

生命保険料控除には新契約と旧契約があります。今入っている保険が新契約か旧契約かわからないという場合も、保険会社から送られてくる保険料払込証明書を見ればどちらか書かれています。
新契約
2012年1月1日以降に結んだ契約が対象です。今後、契約する保険はすべてこちらの制度になります。
旧契約
2011年12月31日以前に結んだ契約が対象です。旧契約には介護医療保険料控除の区分がありません。
新契約と旧契約は控除される上限額が異なります。まとめると、以下の表のようになります。
新旧各契約における生命保険控除の適用限度額
| 旧契約 (2011年12月31日まで) |
新契約 (2012年1月1日から) |
|
| 一般生命保険料控除 | 所得税5万円、住民税3万5,000円 | 所得税4万円、住民税2万8,000円 |
| 介護医療保険料控除 | なし | 所得税4万円、住民税2万8,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 所得税5万円、住民税3万5,000円 | 所得税4万円、住民税2万8,000円 |
| 各控除の合計限度額 | 所得税10万円、住民税7万円 | 所得税12万円、住民税7万円 |
※各区分の上限は2万8,000円ですが、各控除を合計した限度額は7万円となります。
生命保険料控除の計算式

生命保険料控除の金額は、新契約と旧契約で計算方法が異なるため、以下にそれぞれ紹介します。
新契約の場合
新契約による新生命保険料控除、介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除の支払金額に応じた控除額は、以下のとおりです。
所得税控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| ~2万円 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円1円~4万円 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
| 4万1円~8万円 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 8万1円~ | 一律4万円 |
※所得税の各生命保険控除を合計した適用限度額は12万円となります。
住民税控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| ~1万2,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 1万円2,001円~3万円2,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 3万2,001円~5万6,000円 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 5万6,001円~ | 一律4万円 |
※住民税の各生命保険控除を合計した適用限度額は7万円となります。
旧契約の場合
旧契約による旧生命保険料控除と旧個人年金保険料控除の支払金額に応じた控除額は、以下のとおりです。
所得税控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| ~2万5,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円5,000円~5万円 | 支払保険料等×1/2+1万2,500円 |
| 5万1円~10万円 | 支払保険料等×1/4+2万5,000円 |
| 10万1円~ | 一律5万円 |
※所得税の各生命保険控除を合計した適用限度額は10万円となります。
住民税控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| ~1万5,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 1万円5,000円~4万円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 4万1円~7万円 | 支払保険料等×1/4+1万7,500円 |
| 7万1円~ | 一律3万5,000円 |
※住民税の各生命保険控除を合計した適用限度額は7万円となります。
新契約と旧契約が両方ある場合
2011年12月31日までに結んだ契約と、2012年1月1日以降に結んだ契約が両方ある場合は、以下の3つの方法から選ぶことができます。
旧契約のみで申告
旧契約の保険のみ、旧契約の計算表に当てはめて計算します。
新契約のみで申告
新契約の保険のみ、新契約の計算表に当てはめて計算します。
旧契約と新契約の両方で申告
旧契約の保険と新契約の保険で合計できますが、ひとつの種類における合計額は所得税4万円、住民税2.8万円が上限になります。全体の上限額は所得税が12万円、住民税が7万円で、新契約と同一です。
生命保険料控除で具体的にいくら得をする?

先述したように、生命保険料控除は所得控除です。所得控除額がすべて軽減されるのではなく、所得控除×税率が得をする金額です。
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類の生命保険にそれぞれ年間8万円以上支払っている場合、所得控除の金額は所得税12万円、住民税7万円になります。所得税率は課税所得に応じて変わるため、生命保険料控除による軽減額は以下の表のとおりです。
所得税12万円、住民税7万円の場合の生命保険料控除による軽減額
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の軽減額 | 住民税率 | 住民税の軽減額 | 軽減額合計 |
| 1,000~194万9,000円 | 5% | 6,000円 | 10% | 7,000円 | 1万3,000円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 1万2,000円 | 10% | 7,000円 | 1万9,000円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 2万4,000円 | 10% | 7,000円 | 3万1,000円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 2万7,600円 | 10% | 7,000円 | 3万4,600円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 3万9,600円 | 10% | 7,000円 | 4万6,600円 |
なお、課税所得は年収とは異なります。会社員の場合、源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いたものです。
個人事業主の場合は、年間の売上などの収入から、支出した必要経費と所得控除を差し引いたものになります。
そのほかの保険料控除
所得控除の対象となる保険は生命保険だけではありません。給与所得者の保険料控除申告書は、左半分が生命保険料控除、右半分はそのほかの保険料控除になっています。生命保険料以外の保険料控除の種類を見ていきましょう。

1.地震保険料控除
その年に支払った地震保険料の金額に応じて控除が受けられる制度です。地震保険料の場合、支払金額が5万円以下なら支払金額の全額、5万円を超える場合は一律5万円が控除額になります。
2006年12月31日までに契約した旧長期損害保険がある場合、そちらも地震保険料控除の対象になります。上限は1万5,000円です。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額が適用されますが、控除額の上限は5万円までと決まっています。
2.社会保険料控除
国民年金や国民年金基金、健康保険や介護保険など、社会保険料の金額が控除できる制度です。支払った全額が控除対象なので、大きな節税効果が期待できます。
会社員の場合は年金や健康保険が給与から天引きされるため、申告書に記入しなくても会社側で計算してくれます。
ただし、年の途中で就職し、それまで自分で国民年金や国民健康保険に入っていた場合には、支払額を明記して証明書を添付する必要があります。
また、本人が加入者でなくても、生計を同一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料なら対象になります。例えば20歳を過ぎた子供の国民年金を支払ったケースや、扶養に入っていない配偶者の国民年金保険料を支払ったケースが対象となります。
3.小規模企業共済等掛金控除
ここには以下の4種類が含まれます。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
- 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
中でも多くの人に関係があるのが「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」で、iDeCoの掛金が全額控除できます。
生命保険料控除では3つの区分に8万円ずつ、計24万円支払っていたとしても、所得税12万円、住民税7万円のみ対象になります。一方、iDeCoに月2万円、年間24万円投資した場合、所得税で24万円、住民税で24万円が所得控除となります。所得税率10%の人は年間4万8,000円が節税でき、生命保険料控除の節税額の1万9,000円を大きく上回ります。
年末調整や確定申告は漏れのないように申請しよう

年末が近づくと、保険会社からその年の保険料払込証明書が送られてきます。複数の保険に入っていると管理が煩雑になりがちですが、一ヶ所にまとめておくなどして紛失しないよう注意しましょう。
生命保険料控除は会社員の場合は年末調整で対応しますが、個人事業主の場合は確定申告で計算して所得税や住民税を納めます。その際、クレジットカードでの支払いが便利です。

このテーマに関する気になるポイント!
-
生命保険料控除とは?
1年間に支払った生命保険料の金額に応じて、課税所得が控除される制度です。所得税で最高12万円×税率、住民税で最高7万円×10%の節税になります。
-
生命保険料の新契約と旧契約とは?
新契約は2012年1月1日以降に結んだ契約、旧契約はそれ以前に結んだ契約です。
-
生命保険料控除はどうやって受ける?
会社員の場合は、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出すれば、年末調整で処理されます。個人事業主の場合は確定申告で計算をし、申請を行う必要があります。
この記事をチェックした人におすすめの記事 |
|
|
|
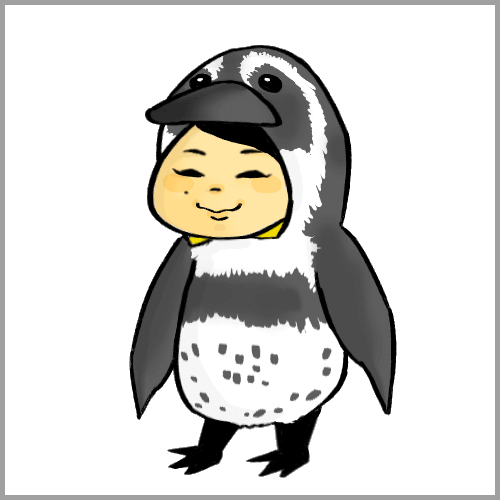
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
![押さえておきたい生命保険『楽天生命保険』の情報はこちらをクリック[PR]](
/woman/assets/article/img/seimei.jpg
)












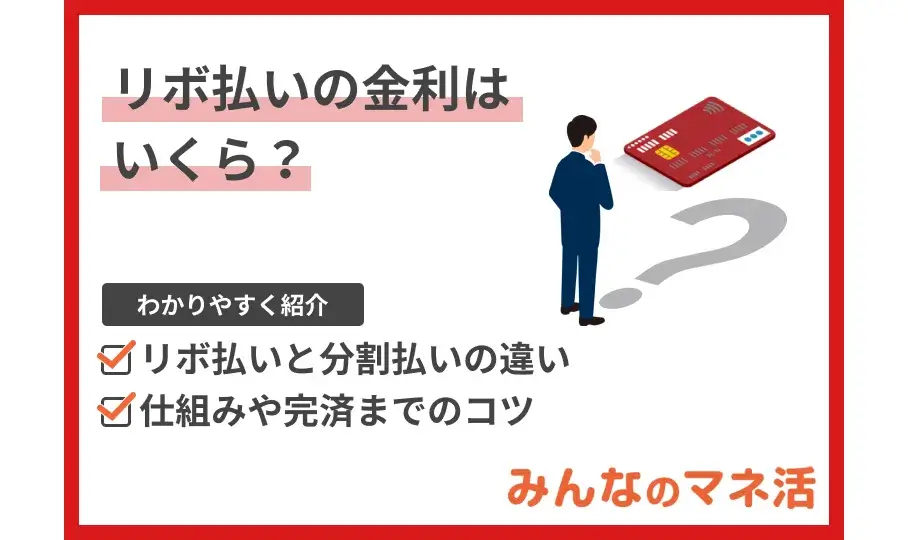


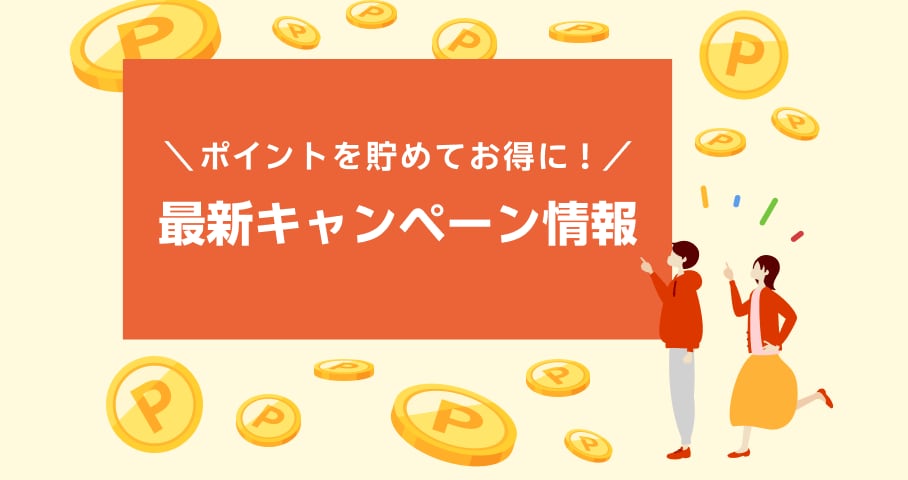







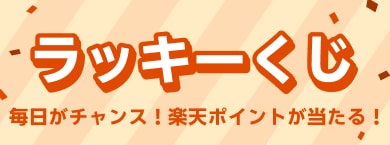


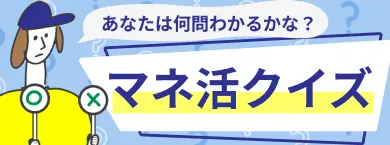
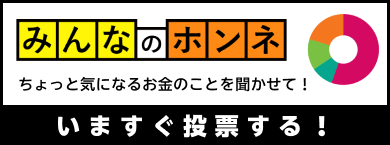
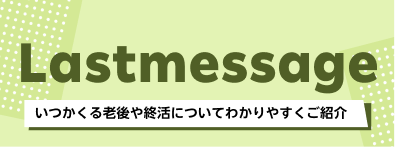
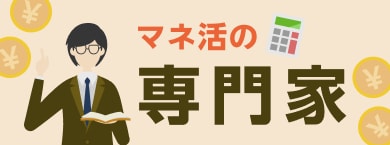








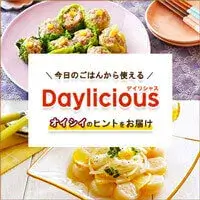




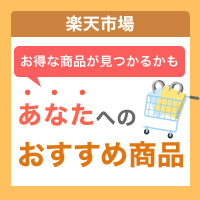
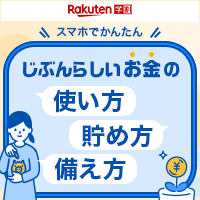
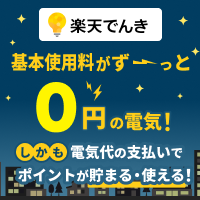


新契約と旧契約の両方を申告したときの全体の控除上限額は、新契約と同じになるのね!