楽天カード会員専用オンラインサービス『楽天e-NAVI』を徹底解説
所得税の計算方法は?所得区分や控除の種類、納付方法も解説
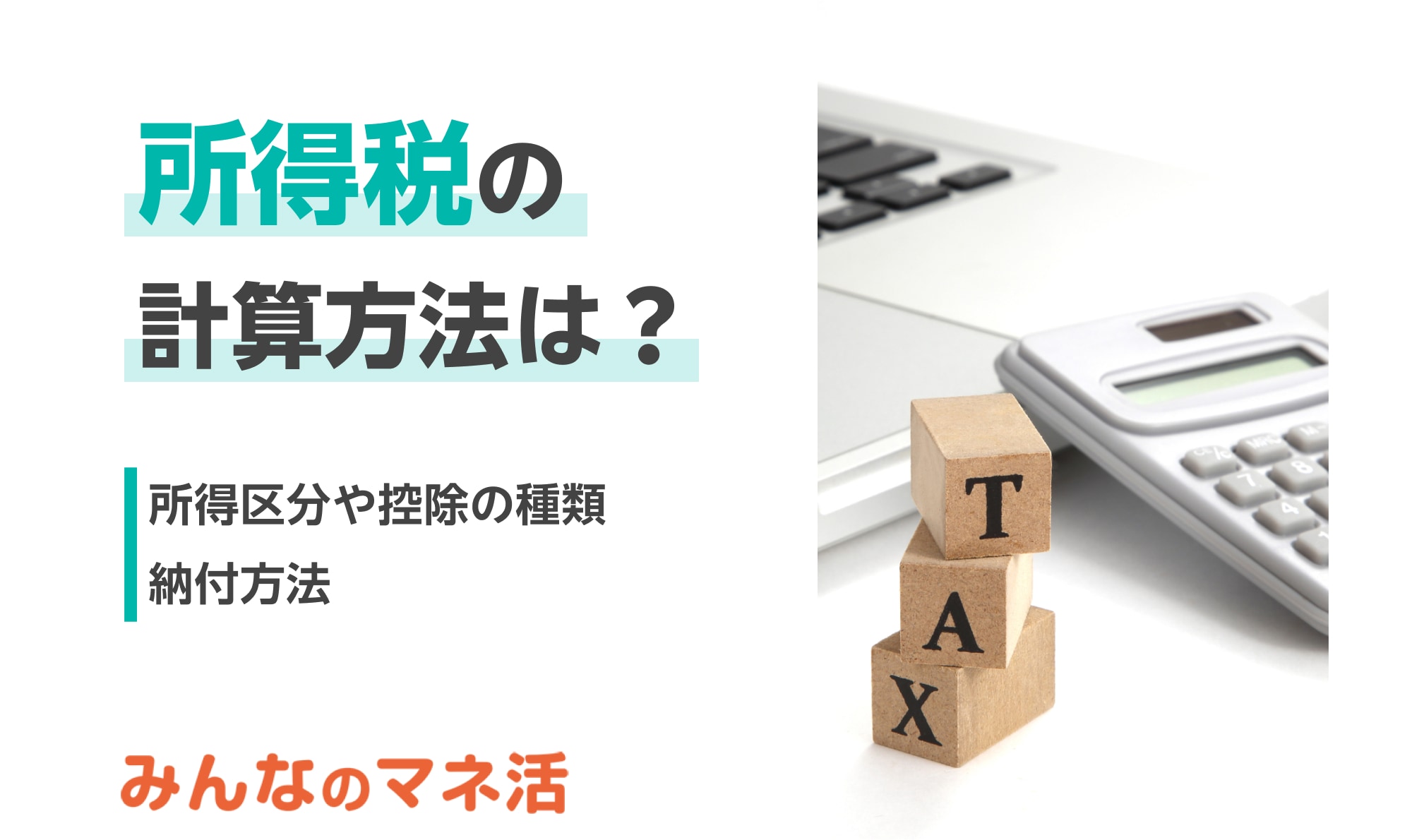
所得税は、給与や事業収入などの所得に対して課せられる税金です。払っていることは把握していても、詳しい計算方法は知らないという方は多いのではないでしょうか。
ここでは、所得税を計算する方法や控除の種類についてまとめました。所得税額を把握したい方や確定申告を利用する方は、ぜひ参考にしてみてください。
所得税とは

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入に対してかかる税金です。ただし、給与の総額にかかるわけではありません。例えば、会社員の場合は給与から「給与所得控除」や「所得控除」を差し引いた金額に対して課税されます。
所得税の税率
所得税の税率は課税される所得金額によって異なります。所得に応じて7段階の税率が設定されており、累進課税制度が適用されています。そのため、課税所得金額が多ければ多いほど所得税率は高くなります。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額(税額控除額) |
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~649万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
※1,000円未満は切り捨て
所得税が課税される年収

所得税は働き方によって課税される年収が異なります。それは、税負担を軽くする控除が働き方によって異なり、控除を利用することで収入があっても所得税がかからない場合があるためです。ここでは、会社員、パート・アルバイト、個人事業主それぞれの所得税がかかる年収について解説をします。
会社員
会社員の場合、すべての納税者が受けられる「基礎控除」と給与所得者だけが受けられる「給与所得控除」の2種類の控除が適用されます。
所得金額が2,400万円以下で基礎控除が48万円、所得金額が162万5,000円以下の場合は給与所得控除が55万円となるため、年間の所得金額が2種類の控除の合計である103万円を超えると所得税がかかります。ただし、そのほかの控除が適用される場合は非課税の範囲が広がる場合もあります。
基礎控除の金額
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0万円 |
給与所得控除の金額
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
| 162万5,000円まで | 55万円 |
| 162万5,001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) |
パート・アルバイト
パートやアルバイトの収入も給与所得にあたり、会社員と同じく「基礎控除」と「給与所得控除」が適用されます。会社員と同じく年収103万円以下で税金がかかるため、月収に換算すると8万5,834円を超えると所得税がかかります。
個人事業主
個人事業主は、事業で利用した経費も総収入から差し引いて所得税が計算されます。会社員やパート・アルバイトと違い、「給与所得控除」がなく「基礎控除」が適用されるため、合計所得金額が2,400万円以下なら基礎控除48万円が適用されます。そのため、個人事業主は課税所得が48万円を超える場合に所得税がかかるといえるでしょう。
なお、会社員やパート・アルバイトが、副業の収入や給与以外の所得での年間所得が20万円以上になった場合、確定申告をする必要があります。年間所得が20万円以下の場合も副業による収入がある場合は住民税の課税対象となるため、自分の住む地域の役所などで忘れずに手続きをするようにしましょう。
所得税の計算方法
所得税額は以下の計算式で求めることができます。
以下から具体的な手順についてご紹介をします。

① 1年間の収入金額を計算する
年間の収入金額は、会社員やパート・アルバイトの場合はボーナスを含めた年間の給与の総額です。個人事業主の場合は年間の事業収入にあたります。
② ①から給与所得控除や経費を差し引く
会社員やパート・アルバイトの場合は、先程ご紹介した給与所得控除を差し引きます。給与所得控除の額は自身の年収に応じて変わるため、事前に確認をしましょう。個人事業主は人件費や家賃など、税法上経費と認められるものを差し引きます。
③ ②から所得控除額を差し引く
所得控除とは、個人の生活状況に合わせて税負担を軽減するための控除です。主なものとして、災害や盗難などで資産に損害が受けた際に適用される雑損控除、生命保険料や介護医療保険を支払った際の生命保険料控除などがあります。
④ ③に所得税の税率をかける
③で計算した課税所得額に、最初に紹介した所得税の税率をかけ合わせます。自身の課税所得金額に応じた税率を確認しましょう。
また、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税として「所得税の金額×2.1%」が加算されます。
⑤ ④から税額控除を差し引く
税額控除とは、所得税の金額から一定の金額を差し引ける制度です。国内株式などの配当金がある場合に適用される配当控除や、一定の要件を満たす住宅の新築や改築をした際の住宅借入金等特別控除などがあります。
税額控除を差し引いた金額が最終的に納税する所得税の金額となります。
|
|
|
所得税を抑える方法

これまで紹介した所得税について、なるべく抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか。そこで、所得税を抑えるために知っておきたい節税方法についてご紹介します。
所得控除や税額控除を活用する
所得税には、税金の負担を軽減させるための制度として所得控除と税額控除があります。これらは個人の生活状況や事情に合わせて適用されるため、該当する控除があるか確認をしてみましょう。
所得控除の例
| 控除の種類 | 主な適用条件 |
| 雑損控除 | 災害や盗難などにより損害を受けたときに適用される |
| 医療費控除 | 10万円(※1)を超えて医療費を支払ったときに適用される |
| 生命保険料控除 | 生命保険料や個人年金保険料などに適用される |
| 寄付金控除 | ふるさと納税や特定の団体に寄付をしたときに適用される |
| 寡婦控除 | 配偶者と死別・離婚し、扶養家族がいる場合に適用される |
| ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親のときに適用される |
| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円以下のときに適用される |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下のときに適用される |
※1 所得が200万円未満のときは、所得金額×5%を超えた分の医療費が控除額になります。
税額控除の例
| 税額控除 | 主な適用条件 |
| 配当控除 | 国内株式からなどの配当金が収入としてある場合 |
| 外国税額控除 | 外国企業からの収入があり、すでにその国の所得税が課されたとき |
| 住宅借入金等特別控除 | 住宅ローン等を利用してマイホームの新築や増改築をした場合 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 1981年5月以前に建てられ、現在も住んでいる住居に耐震工事をした場合 |
| 住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリーや多世帯同居のための改修工事を行った場合 |
iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、「投資信託」や「定期預金」などの運用商品の中から自分で掛金を設定し、運用をすることで資産を形成する私的年金制度です。基本的に20歳以上65歳まですべての方が加入でき、運用した掛金は60歳以上に老齢給付金として受け取ることができます(※)。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税を抑えることができます。また、運用益も非課税で資産を蓄えることができます。
※ 受取開始には、最低10年間の加入期間が必要です。
所得税の納税方法
所得税の納税方法は、会社員などの給与所得者か個人事業主かによって異なります。以下でそれぞれの納税方法を解説します。
会社員の場合
会社員の場合は、自分の勤務する会社など雇用主を通じて所得税が源泉徴収されるので、個人で納める必要はありません。納付した所得税額(源泉所得税額)については、給与明細書で確認できます。
ただし、以下に当てはまる場合は確定申告をして、所得に応じた所得税額を納付しなくてはいけません。
- 給与所得や退職所得以外に所得があり、その所得が年間20万円を超える(2カ所以上から給与を受け取っている場合は、年末調整されなかった所得と給与所得以外の所得の合計で計算する)
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 同族会社の役員などで、同族会社から貸付金の利子、資産の賃貸料などを受け取っている
- 災害減免法により、源泉徴収の猶予を受けている
- 退職所得にかかる所得税額が、源泉徴収された金額よりも多い
- 源泉徴収義務のない者から給与などを受け取っている
個人事業主の場合
自営業やフリーランスなどの個人事業主の場合は、基本的に自身で所得税を納める必要があります。年間の所得を合算し、控除を差し引いて所得税額を計算したうえで定められた期間に確定申告の手続きをします。なお、源泉徴収された状態で受け取った収入に関しては、確定申告の際に源泉所得税額を記入します。
納税方法は以下のとおりです。
- クレジットカード納付
- e-Taxによる電子納税
- QRコードまたはバーコード利用してコンビニで納付
- 金融機関または税務署の窓口で現金納付
- 金融機関の口座から振替納税
- スマホアプリで納付
e-Taxやスマホアプリを利用したオンライン納付もできるため、自分の都合に合わせて納付を行いましょう。
確定申告は青色申告にする
個人事業主が確定申告する際は、青色申告で行うようにしましょう。確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告は特別控除があり、最大65万円を所得から差し引くことができます。
青色申告を行う際はe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存に加え、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。事前に準備が必要なものについてしっかりと確認し、対応をしましょう。
所得税はクレジットカードで納付できる

所得税を自身で納める場合、「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubといった国際ブランドで納付が可能です。
給与所得のみの方は所得税を自身で納付する必要はありませんが、副業などでほかの所得を得ている方や事業所得などがある方は、クレジットカードでの納付も検討してみましょう。クレジットカードで納付するメリットと注意点について、それぞれ解説します。
クレジットカードで所得税を納付するメリット
クレジットカードで所得税を納付すると、次のメリットがあります。
- クレジットカードのポイントを貯められる
- 24時間いつでもどこでも納付できる
- 支払回数などを変更できることがある
クレジットカードのポイントを貯められる
クレジットカードで支払うと、ポイントが貯まる場合があります。ポイント還元サービスがあるか、税金の支払いでどれくらいのポイントが進呈されるかはクレジットカード会社により異なるため、事前に確認しましょう。
24時間いつでもどこでも納付できる
また、カード払いはオンラインで完結するので、税務署や金融機関の営業時間以外も納付が可能です。平日の日中は忙しい方も、カード払いを検討しましょう。
支払回数などを変更できることがある
支払回数を選べるのもクレジットカードで払うメリットです。通常であれば所得税はまとめて納付しなくてはいけませんが、クレジットカードなら分割払いやリボ払いを選択できる場合があります。
クレジットカードで所得税を納付する際の注意点
クレジットカードで納付するときは、次の点に注意が必要です。
- 決済手数料が発生する
- 手続きの取り消しができない
決済手数料が発生する
納付額が増えるほど還元されるポイントも増えますが、決済手数料も高くなる点に注意しましょう。決済手数料は納付額に応じて以下の金額です。
| 納付額 | 決済手数料(税込み) |
| 1円~1万円 | 99円 |
| 1万1円~2万円 | 198円 |
| 2万1円~3万円 | 297円 |
| 3万1円~4万円 | 396円 |
| 4万1円~5万円 | 495円 |
5万1円以降も同様に、1万円を超えるごとに決済手数料が99円(税込み)加算されます。
事前に納付する金額に対してどれくらいの決済手数料がかかるか、確認しておくと良いでしょう。
手続きの取り消しができない
国税クレジットカードお支払サイトで納付した場合、手続きの取り消しはできません。誤った内容で手続きしてしまった場合、所轄の税務署に連絡して還付等の手続きを行う必要があります。納付の際は入力項目が誤っていないかしっかりと確認をするようにしましょう。

所得税をクレジットカードで納付するなら楽天カードがおすすめ

所得税をクレジットカードで納付するなら、年会費永年無料の楽天カードがおすすめです。Visa、Mastercard、JCB、American Express(※1)から好きな国際ブランドが選べて、いずれの国際ブランドも所得税の支払いに対応しているので、納税用のクレジットカードとして活用できます。また、楽天カードを利用して所得税を納付すると500円につき楽天ポイントが1ポイント(※2)貯まるため、手軽にポイントを貯めることができます。
「国税クレジットカードお支払サイト」では、所得税以外の法人税、相続税、贈与税などもクレジットカードで納付(※3)できます。ポイントを効率よく貯める手段として、また、期限内に手間をかけずに納税する手段として、楽天カードを活用しましょう。
※1 アメリカン・エキスプレス®のカードは、アメリカン・エキスプレスのライセンスにもとづき楽天カード株式会社が発行・運営しております。
※2 カードの利用獲得ポイントの還元率について、詳細はこちらをご確認ください。
※3 納付税額に応じて決済手数料がかかります。
【年会費永年無料】楽天カード
※この記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しております。



-
年会費が永年無料
-
100円につき1ポイント貯まる※2
- ※1 新規入会特典2,000ポイント(通常ポイント)、カード利用特典8,000ポイント(うち6,000ポイントは期間限定ポイント、2,000ポイントは通常ポイント)。特典の進呈条件について詳細を見る
- ※2 一部ポイント還元の対象外、または還元率が異なる場合がございます。ポイント還元について詳細を見る
このテーマに関する気になるポイント!
-
給与所得者は所得税を支払う必要がある?
一定以上の所得があれば支払う必要があります。しかし、給与から源泉徴収されているので、副業などの所得がほかにないときは個人的に納税手続きをする必要はありません。
-
所得税の控除って何?
控除とは支払金額を差し引くことです。所得控除は課税所得金額を求めるときに差し引く金額、税額控除は実際に支払う所得税額を求めるときに差し引く金額です。
-
所得税の納税にクレジットカードを使うとどんなメリットがある?
納付額にあわせてクレジットカードのポイントが貯まる場合があります。また、時間を選ばずに納税できる点もメリットです。
この記事をチェックした人におすすめの記事 |
|
|
|
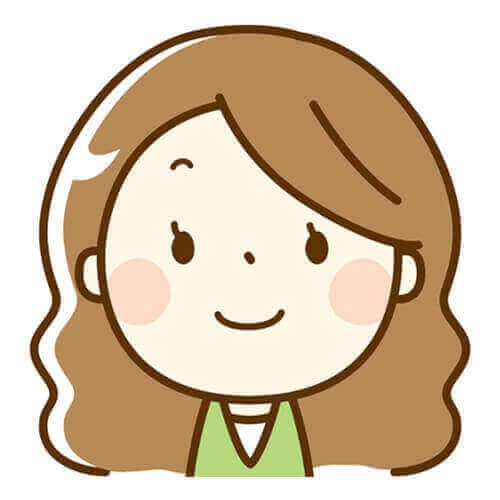
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。












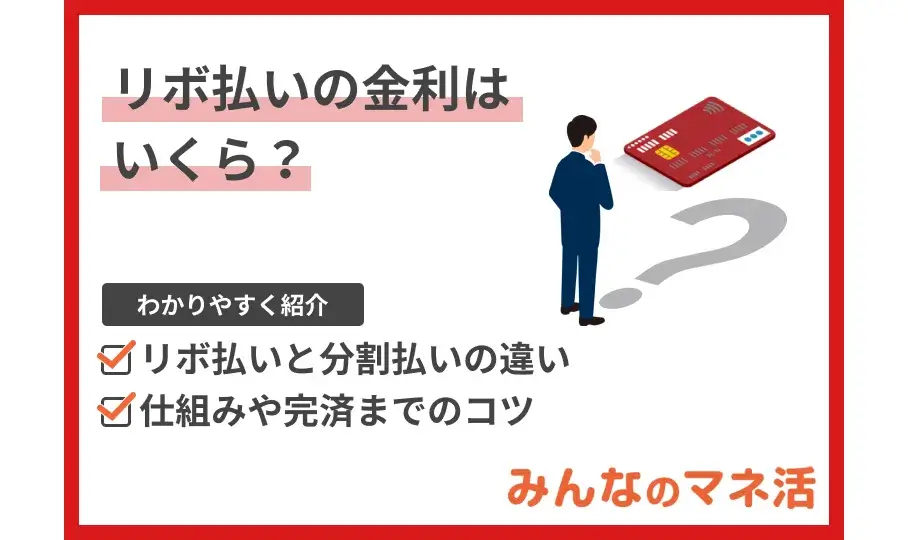


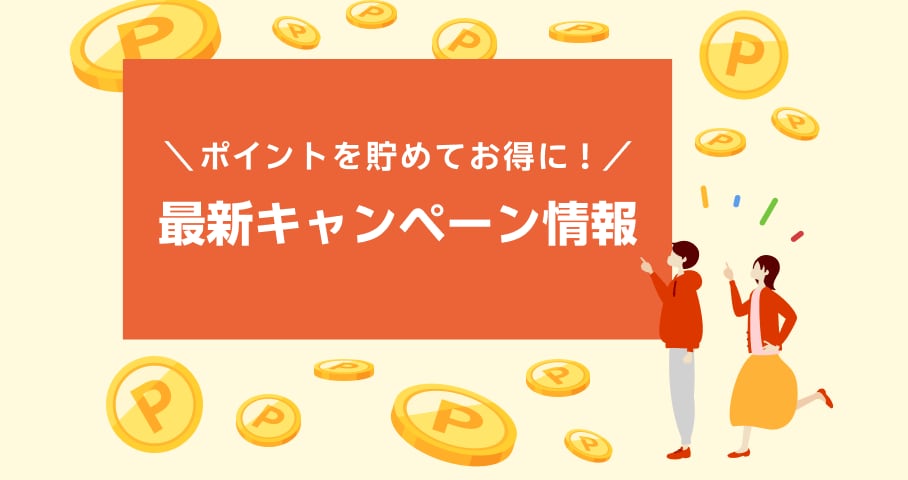







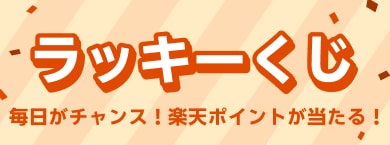


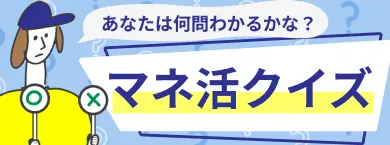
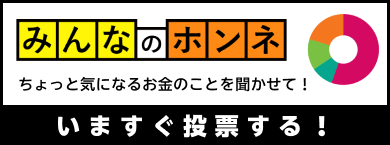
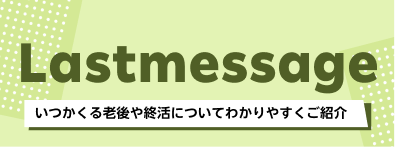
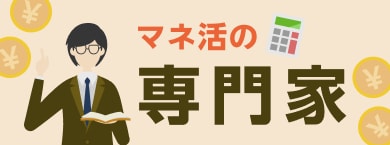








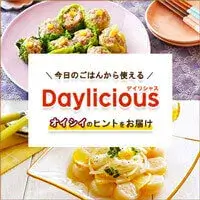




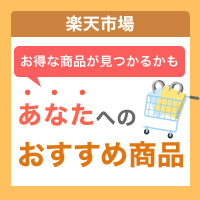
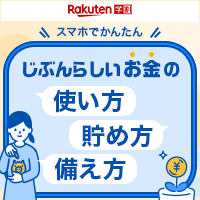
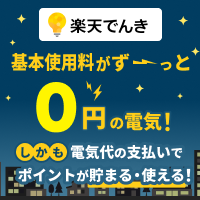


会社員やパート・アルバイトは年収103万円、個人事業主は年収48万円を超えると所得税がかかるのね!